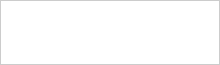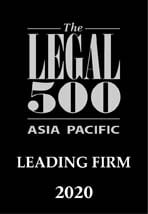知的財産高等裁判所第4部(宮坂昌利裁判長)は、令和6年(2024年)4月24日、「レーザー加工装置」「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」との名称の特許に係る特許権侵害を理由とする事案において、原告が被告による特許発明の実施品ではなくその部品を製造販売していた場合において、102条2項を適用し、被告製品中の特許発明の実施品の価格に相当する割合に基づき損害額を認定しました。
知的財産高等裁判所第4部(宮坂昌利裁判長)は、令和6年(2024年)4月24日、「レーザー加工装置」「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」との名称の特許に係る特許権侵害を理由とする事案において、原告が被告による特許発明の実施品ではなくその部品を製造販売していた場合において、102条2項を適用し、被告製品中の特許発明の実施品の価格に相当する割合に基づき損害額を認定しました。
特許権者と侵害者の製品市場が異なる場合に特許法102条2項に基づく損害の算定が認められるかは実務上の1つの論点ですが、本判決は、原告が被告による特許発明の実施品の完成品ではなく部品を製造販売していた場合において特許法102条の適用される場面と、その具体的な計算方法を示した点において、実務上参考になるといえます。
なお、本判決と同一の原告と被告との間で、同一の被疑侵害品につき異なる特許権の侵害が争われた事案では、特許法102条2項に基づく損害額の算定を認めず、同一の事実関係の下で異なる判断がなされています。こちらの判決についても「関連事件」として紹介します。
ポイント
骨子
- 特許法102条2項は損害の推定規定にとどまるものであり、同項の適用を認めたからといって、当然に侵害者利益額の全額が損害として認められるわけではなく、侵害者の利益額と特許権者の損害額との間の相当因果関係の一部についてであっても、推定を破る事情が立証されれば、部分的又は割合的に推定を覆滅させることを認めるべきであり、そうした柔軟な手法による合理的な解釈運用が可能である。このような点を踏まえると、同項を適用するための要件を殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきであり、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められる。
- ステルスダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、被控訴人からSDエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されていること、被控訴人製SDエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品にとどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品の構成中、被控訴人製SDエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解されることからすると、本件において、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば特許権者に利益が得られたであろうという事情が認められるというべきである。(特許権者が販売する部品を用いて生産された完成品と、侵害者が販売する完成品とは、同一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りでは、特許権者による部品の販売行為は、当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害品(完成品)の譲渡行為と間接的に競合する関係にある。)
- 特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ販売等することができたという競合関係にある製品をいう(知的財産高等裁判所平成31年(ネ)第10003号令和2年2月28日特別部判決参照)。
- ステルスダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、被控訴人からSDエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されていること、被控訴人製SDエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品にとどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品の構成中、被控訴人製SDエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品としての競争力の源泉となっているものと解されることからすると、被控訴人製SDエンジンは、侵害行為によって販売数量に影響を受けるものと認められ、本件において、特許法102条1項所定の「その侵害行為がなければ販売することができた」という関係が認められる。
判決概要
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第4部 |
|---|---|
| 判決言渡日 | 令和6年4月24日 |
| 事件番号 | 令和5年(ネ)第10052号、第10080号、令和6年(ネ)第10002号 特許権侵害差止等請求控訴、同附帯控訴、民訴法260条2項の申立て事件 |
| 裁判官 | 裁判長裁判官 宮 坂 昌 利 裁判官 本 吉 弘 行 裁判官 岩 井 直 幸 |
【関連事件】
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第2部 |
|---|---|
| 判決言渡日 | 令和6年3月6日 |
| 事件番号 | 令和5年(ネ)第10037号 特許権侵害差止等請求控訴事件 |
| 裁判官 | 裁判長裁判官 清 水 響 裁判官 浅 井 憲 裁判官 勝 又 来 未 子 |
解説
特許権侵害における損害額の推定規定
特許法における損害額の推定規定
特許権侵害に基づく損害賠償の請求においては、特許権者または専用実施権者(以下「特許権者等」といいます。)における損害額の立証困難軽減の趣旨から、損害額の推定規定が置かれています。
(損害の額の推定等)
第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
5 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
この規定の構造として、3項は実施料相当額をもって損害の最低額とみなし、2項は侵害者が侵害行為によって得た利益をもって特許権者等の侵害とみなし、1項は侵害品の販売数量に特許権者等の利益率を掛け合わせることによって損害を計算することを認めています。
また、1項では、特許権者等の実施能力を超えた数量部分については、3項の実施料相当額についても損害の額とすることを認めており(第2号)、2項においても、明文規定はないものの、1項と同様に、特許権者の実施能力を超えた数量部分につき、実施料相当額の損害を請求できるものと解されています(知財高判令和4年10月20日椅子式マッサージ機事件判決)。
損害額の推定規定が適用されるための要件
特許法の条文においては、前記102条1項及び2項の損害額の推定規定が適用されるための要件は、102条1項については、侵害者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したとき、同条2項については、侵害者がその侵害の行為により利益を受けているときです。
特許権者と侵害者の実施態様や市場が異なる場合に推定規定は適用されるかについて争いがあります。
この点につき、102条1項の適用について、知財高裁は、同条項の「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者の製品であれば足りると判断しています(競合品十分説。知財高判令和2年2月28日美容器事件判決)。
また、102条2項については、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められ、特許権者において当該特許発明を実施していることは同条項の要件ではないと判断しています(知財高判平成25年2月1日ごみ貯蔵機器事件判決、同令和元年6月7日二酸化炭素含有粘性組成物事件判決)。
事案の概要
背景事実
原告は、発明の名称を「レーザー加工装置」「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」と題する特許(登録番号:特許第3867108号及び第4601965号)。以下、併せて「本件特許」といいます。)を保有する者であったところ、一定の条件でレーザ光をウェハ内部に集光してウェハ内部において加工層を形成し、その後ウェハに引っ張り応力を加え、ウェハ表面に形成される集積回路に損傷を与えずに加工層を起点としてウェハを分割することを、ステルスダイシング(Stealth Dicing)と呼び、ステルスダイシングを行う装置(以下、本稿において、「SDダイサー」、「ステルスダイサー」または「SD装置」といいます。)の中核モジュールであるSDエンジンを製造・販売していました。
SDダイサーとSDエンジンは、ともに本件特許発明の実施品であり、また、後者が前者の構成部品の一部であるという関係にありました。原告のビジネスモデルは、SDダイサーのメーカーに対してSDエンジンを販売するとともに、購入者に対して本件特許を含む特許及びノウハウを「包括技術ライセンス」の契約に基づき許諾をするというものでした。
原告はこの包括技術ライセンスを自社のSDエンジンの購入者に対してのみ許諾する方針をとっており、自社技術のライセンスのみをするというビジネスは行っていませんでした。なお、原告自身はSDダイサーを製造または販売するという事業は行っていません。
一方、被告はSDダイサーの製造販売を行う事業者であり、その顧客は半導体メーカーでした。被告と原告は業務提携契約を締結の上、被告が原告からSDエンジンを購入する等の取引がありましたが、被告は、同契約の終了後に独自に開発したSDエンジンを搭載したSDダイサーを製造し、自社の顧客に販売するようになりました。
以上のとおり、本件では、原告は被告の製品を構成する部品を製造する企業であり、原告の顧客がSDダイサーという装置メーカーであるのに対し、被告の顧客は半導体メーカーであるという点で製品の市場を異にしていました。
| 原告(特許権者) | 被告 | |
|---|---|---|
| 製 品 | SDエンジン(特許発明の実施品) | SDダイサー(特許発明の実施品を含む装置) |
| 需要者 | SDダイサーのメーカー | 半導体メーカー |
訴えの提起
原告は、被告の製造販売するSDダイサー内のSDエンジンが原告の特許権を侵害すると主張して、被告に対してSDダイサーの製造販売等の中止を求めたものの被告が応じなかったため、被告に対して、被告の行為が本件特許権を侵害するものと主張して、損害賠償の請求を行いました。また、原告は、損害賠償請求につき、102条1項ないし3号に基づく損害を選択的に主張していました。
本件の争点は多岐にわたっていますが、本稿では、損害論に関する争点のみを取り上げます。
原判決
原判決(東京地判令和4年12月15日)は、被告による特許権侵害を認めました。そのうえで、損害論については次のように判断しました。
まず、特許法102条2項の適用可否については、「特許権者において販売等する製品が、侵害品の部品に相当するものであり、侵害品とは需要者を異にするため、市場において競合関係に立つものと認められない場合」には特許法102条2項は適用されないと述べた上で、本件では、特許権者である原告が販売する製品(SDエンジン)は、侵害品であるSDダイサーの部品に相当するものであり、SDダイサーとは需要者を異にするため、市場において競合関係に立つものと認めることはできないとして、同条項の適用を否定しました。
また、102条1項の適用については、SDエンジンはSDダイサーの部品であるところ、特許権者である原告が販売する製品(SDエンジン)は、侵害品であるSDダイサーの部品に相当するものであり、SDダイサーとは需要者を異にするため、市場において競合関係に立つものと認めることはできないと述べ、適用を否定しました。
なお、原判決は、102条3項の実施料率を30%と非常に高い割合を認定し、同条項に基づき15億円を超える損害額を認定しています。
これに対して、原告が控訴、被告が附帯控訴をしていました。
判旨
特許法102条2項の適用について
知財高裁も原審同様特許権侵害を認めましたが、原判決とは異なり、本件の取引の実情を具体的に認定の上、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば特許権者に利益が得られたであろうという事情」が認められると判断し、102条2項の適用を認めました。
判決では、102条2項の趣旨につき、損害の推定規定にとどまるものとし、同項の適用を認めたからといって、当然に侵害者利益額の全額が損害として認められるわけではないから、推定の覆滅により柔軟な手法による合理的な解釈運用が可能であると述べています。
(特許法102条2項は)損害の推定規定にとどまるものであり、同項の適用を認めたからといって、当然に侵害者利益額の全額が損害として認められるわけではなく、侵害者の利益額と特許権者の損害額との間の相当因果関係の一部についてであっても、推定を破る事情が立証されれば、部分的又は割合的に推定を覆滅させることを認めるべきであり、そうした柔軟な手法による合理的な解釈運用が可能である。このような点を踏まえると、同項を適用するための要件を殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきであり、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められる。
その上で、本件におけるあてはめにつき、原告と被告の市場が異なるものの、ステルスダイサーの国内での販売者は被告のほか1社であること、SDエンジンはステルスダイサーの製品に不可欠な技術の中核であることを重視し、「特許権者による部品の販売行為は、当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害品(完成品)の譲渡行為と間接的に競合する関係にある」との評価がされています。
ステルスダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、被控訴人からSDエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されていること、被控訴人製SDエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品にとどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品の構成中、被控訴人製SDエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解されることからすると、本件において、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば特許権者に利益が得られたであろうという事情が認められるというべきである。(特許権者が販売する部品を用いて生産された完成品と、侵害者が販売する完成品とは、同一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りでは、特許権者による部品の販売行為は、当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害品(完成品)の譲渡行為と間接的に競合する関係にある。)
具体的な損害額の算出は、被告製品の限界利益(被告製品の売上高から、被告において被告製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した額)に、SDエンジンの価額のSDダイサーの価額に占める割合を乗ずる方法で損害額を算定しています(限界利益全額との差額については推定が覆滅されるとしています)。SDエンジンとSDダイサーの価格差は、原告被告双方が開示した資料から、裁判所が「合理的な推認」により認定しました(なお、具体的な割合は判決文では閲覧制限がかけられているため、確認ができません)。
結論として、裁判所は102条2項に基づき、計7億5,628万7,981円を損害額として認定しました。
特許法102条1項の適用について
次に、特許法102条1項の適用について、原審と同様に美容器事件の規範を用いていますが、原審とは異なり、侵害の態様を実質的に見て同条項適用を肯定しました。102条1項の適用についても、102条2項に関する判断と同様、原告製品と被告製品の市場及びSDエンジンのステルスダイサー内における技術的な価値を考慮して、実質的な判断をしています。
特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ販売等することができたという競合関係にある製品をいう(知的財産高等裁判所平成31年(ネ)第10003号令和2年2月28日特別部判決参照)。
ステルスダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、被控訴人からSDエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されていること、被控訴人製SDエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品にとどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品の構成中、被控訴人製SDエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品としての競争力の源泉となっているものと解されることからすると、被控訴人製SDエンジンは、侵害行為によって販売数量に影響を受けるものと認められ、本件において、特許法102条1項所定の「その侵害行為がなければ販売することができた」という関係が認められる。
特許法102条3項に基づく損害
原判決は、102条3項の実施料率を30%と非常に高い割合を認定しましたが、本判決は、実施料率は15%と判断しました。
判断を分けたのは、原審は、被告の行為の態様につき、「故意に不正使用して原告の特許権を侵害した」との認定をしたことにあると思われます。本判決はそのような事実認定は行わず、原告の包括ライセンスによる実施料率のほか、業界における実施料率の統計データや、本件各特許の技術的価値等を総合して実施料率を認定しています。
結論としては、102条2項に基づく損害額が最も高くなったため、同条に基づいて算定された損害額が認容されています。(認容額8億3,191万6,753円)
関連事件について
関連事件における請求と第一審の判断
関連事件は、本判決と原告及び被告が同一であり、かつ、同一の被告製品が被疑侵害品として特許権の侵害が争われた事案です。行使された特許権は、発明の名称を「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」と題する特許(登録番号:特許第4509578号)であり、本件同様、原告のステルスダイシング技術に関連する半導体をレーザー加工するための方法及び装置に関する技術になります。
関連事件においても、原告は、損害賠償請求については102条1項ないし3号に基づく損害を選択的に主張していました。
原判決(東京地判令和5年2月15日)は、102条2項の適用要件として「侵害者が特許権侵害行為により受けた利益と同質といえる利益を特許権者が獲得し得るという関係が類型的が認められること」を要求し、本件では、「102条2項適用の基礎を欠く」として、102条2項の適用を否定しました。
他方、特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」は市場で影響を受けるものであれば足りるとした上で、102条1項適用を肯定し、推定の覆滅割合は8割5分として損害額を認定しました。
これに対して、双方が控訴をしていました。
特許法102条2項の適用について
裁判所は、以下のように、ごみ貯蔵機器事件及び二酸化炭素含有粘性組成物事件の規範を引用した上で、本件でもこれらの規範における「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」自体は認められるものと述べました。
特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許権者がその侵害行為により損害を受けたものとして、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである(知的財産高等裁判所平成25年2月1日特別部判決(同裁判所平成24年(ネ)第10015号)、同裁判所令和元年6月7日特別部判決(同裁判所平成30年(ネ)第10063号)、令和4年特別部判決参照)。
本件では、原告のSDエンジンは、SD装置が本件各発明を含むステルスダイシング技術を用いたレーザ加工機能を実現するために必須となる部品であって枢要な機能を担うものであり、被告による被告旧製品(侵害品)の製造及び輸出・販売行為がなかったならば、原告は自らのSDエンジンを被告又は他のSD装置の製造者に販売することにより、輸出・販売された被告旧製品に対応する利益が得られたであろうということはきる。
しかしながら、裁判所は、以下のように、被告製品中の原告製品相当分の限界利益を特定することができないことを理由に、同項に基づく損害認定はできないと判断しました。
しかしながら、原告はSDエンジンを販売していたものであって、侵害品と同種の製品であるSD装置を製造・販売していたものではない。また、原告において自らSD装置を製造する能力があり、具体的にSD装置を製造・販売する予定があったことを認めるに足りる証拠もない。原告の逸失利益はあくまでもSDエンジンの売上喪失によるものであって、SD装置の売上喪失によるものではない。そして、SD装置とSDエンジンとは需要者及び市場を異にし、同一市場において競合しているわけではない。したがって、SD装置の売上げに係る被告の利益全体をもって、原告の喪失したSDエンジンの売上利益(原告の損害)と推定する合理的事情はない。
以上によれば、本件において、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう事情があるとして特許法102条2項の規定の適用が認められるとはいえるものの、SDエンジン相当分の限界利益を特定することができないから、同項の推定規定により本件における原告の損害を認定することはできない。・・・そうすると、本件における原告の損害の認定は、特許法102条2項の推定規定の適用以外の方法で行うのが相当である。
裁判所としては、102条2項が適用されるための事情はあるものの、原告はSD装置を販売していないため、侵害品を組み込んだSD装置全体の売上をもとに損害額を認定することは相当ではないと判断したものと思われます。
特許法102条1項の適用について
特許法102条1項の適用について、裁判所は、以下のとおり、美容器事件の規範を引用の上、本件では、被告の侵害行為がなければ、原告はその製造する原告エンジンを販売することができ、これにより利益を得ることができたものと推認されるとし、102条1項の適用を肯定しました。なお、推定の覆滅割合は、原判決とは異なり、7割と認定しています。
特許法102条1項の文言及び上記趣旨に照らせば、特許権者が「侵害の行為がなければ販売することができた物」(同項1号)とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者の製品であれば足り、特許権者が特許実施品又は専ら特許実施品の生産のために用いる物(部品)を販売しており、侵害行為がなければ、特許権者は自らの製品を販売することができたという関係にある場合には、特許権者は、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける製品を販売していたということができるから、同項の適用が是認される。
そして、本件では、前記(2)のとおり、被告の侵害行為がなければ、原告はその製造する原告エンジンを販売することができ、これにより利益を得ることができたものと推認され、原告は、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける製品である原告エンジンを販売していたということができるから、同項を適用することができる。
一方、102条1項2号の適用は否定しています。
「特許権者が販売することができないとする事情」に相当する数量は、その性質上、特許権者が実施許諾をし得たものとは認められないから、本件では、同項2号の規定を適用して、実施料相当額を加算することはできない。
結論として、102条1項に基づき算出された損害が同条3項に基づく損害を上回ったため、裁判所は1項に基づく損害を認定しています。(認容額は1億3,684万円)
コメント
本判決は、原告は被告製品の一部のユニット(部品)を製造販売しており、原告製品と被告製品の市場が異なるケースにおいて、取引の実情を具体的に見た上で、特許法102条2項の適用を認めた事例として意義があります。
また、関連事件では、102条2項の適用の基礎があることを認めながらも、SDエンジンはSD装置の一部の部品であり、その限界利益を算出できないことから同条項による損害額の算定ができないと判断をしているのに対し、本判決では、SDダイサーとSDエンジンの価格差につき損害額の推定を覆滅するという方法により損害額を認定しました。
もっとも、限界利益の価格差により損害額を算出するという方法は、全てのケースで用いることができることができるとは限らないとも思われます。事案によっては価格差を出すことができないケースもあるでしょうし、製品自体の価格差が大きくても、特許発明の実施品の技術的意義が製品全体において極めて高いようなケース等では価格差のみで部品に相当する限界利益を出すことが適当ではない可能性もあります。
102条1項の適用については、競合品十分説を採用し、緩やかな基準で適用を肯定しており、従前の裁判例の傾向と同様といえるでしょう。
本記事に関するお問い合わせはこちらから。
(文責・町野)