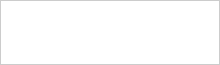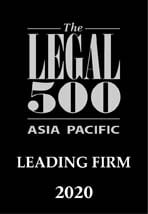最高裁判所第二小法廷(草野耕一裁判長)は、本年(令和7年・2025年)3月3日、ネットワーク関連発明を構成するサーバが海外にあるために、我が国における実施行為といえるかが争われた事案において、日本国内の端末で効果を生じ、サーバが日本国外にあることに特段の意味がないこと、及び、特許権者に経済的な影響を及ぼさないというべき事情がないことを根拠に、実質的に我が国の領域内で実施行為が行われていると評価するのが相当であるとの判断を示しました。
最高裁判所第二小法廷(草野耕一裁判長)は、本年(令和7年・2025年)3月3日、ネットワーク関連発明を構成するサーバが海外にあるために、我が国における実施行為といえるかが争われた事案において、日本国内の端末で効果を生じ、サーバが日本国外にあることに特段の意味がないこと、及び、特許権者に経済的な影響を及ぼさないというべき事情がないことを根拠に、実質的に我が国の領域内で実施行為が行われていると評価するのが相当であるとの判断を示しました。
最高裁判所は、同一裁判体により、同じ日に同一当事者間における2件のファミリー特許にかかる特許権侵害訴訟について同趣旨の判決をしており、うち1件は、知財高裁特別部(大合議)の判決(知財高判令和5年5月26日令和4年(ネ)第10046号特許権侵害差止等請求控訴事件)に対する上告受理申立事件におけるものとなっています。
これらの判決は、ネットワーク関連発明における実施行為の解釈につき、今後の法解釈や法改正の動向にも影響するものと思われます。ここでは、上記大合議判決に対する上告審の判断内容に沿って検討した後に、関連事件についても触れることにします。
ポイント
骨子
- 我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められるが(最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照)、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、当該システムを構築するための行為が特許法2条3項1号にいう「生産」に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。
- そうすると、そのような場合であっても、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における「生産」に当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。
- 本件配信は、プログラムを格納したファイル等を我が国の領域外のウェブサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受信させるものであって、外形的には、本件システムを構築するための行為の一部が我が国の領域外にあるといえるものであり、また、本件配信の結果として構築される本件システムの一部であるコメント配信用サーバは我が国の領域外に所在するものである。しかし、本件システムを構築するための行為及び本件システムを全体としてみると、本件配信による本件システムの構築は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、その結果、本件システムにおいて、コメント同士が重ならないように調整するなどの処理がされることとなり、当該処理の結果が、本件システムを構成する我が国所在の端末上に表示されるものである。
- これらのことからすると、本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によるものである本件配信やその結果として構築される本件システムが、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人は、本件配信及びその結果としての本件システムの構築によって、実質的に我が国の領域内において、本件システムを生産していると評価するのが相当である。
判決概要
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
|---|---|
| 判決言渡日 | 令和7年(2025年)3月3日 |
| 事件番号 事件名 |
令和5年(受)第2028号 特許権侵害差止等請求事件 |
| 原判決 | 知財高判令和5年5月26日 令和4年(ネ)第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件 |
| 裁判官 | 裁判長裁判官 草 野 耕 一 裁判官 三 浦 守 裁判官 岡 村 和 美 裁判官 尾 島 明 |
【関連事件】
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
|---|---|
| 判決言渡日 | 令和7年(2025年)3月3日 |
| 事件番号 事件名 |
令和5年(受)第14号、第15号 特許権侵害差止等請求事件 |
| 原判決 | 知財高判令和4年7月20日 平成30年(ネ)第10077号 特許権侵害差止等請求控訴事件 |
| 裁判官 | 裁判長裁判官 草 野 耕 一 裁判官 三 浦 守 裁判官 岡 村 和 美 裁判官 尾 島 明 |
解説
特許法における属地主義
属地主義と域外適用
「属地主義」とは、自国法を適用する範囲を自国領域内に限る考え方をいいます。立法は国家主権の行使であり、国家主権が及ぶ範囲は自国領域内ですので、法の効果が及ぶ範囲を自国領域内とする属地主義は、法律の地理的適用範囲を決定する原則的な考え方に位置付けられます。
他方、法の地理的適用範囲を自国の領域に限定しない場合もあります。そうした法適用は「域外適用」と呼ばれ、典型的なものとしては、刑法2条ないし4条の2に規定される国外犯があり、属人主義や保護主義に基づく域外適用が認められています。
通常の企業活動に関連する域外適用の例としては、規制対象となる行為の効果が自国に及ぶかどうかを基準とする「効果主義」が代表的で、現在、主要国の独占禁止法の適用基準となっています(効果主義により外国の行為に我が国の独占禁止法を適用した判決として、最判平成29年12月12日平成28年(行ヒ)第233号民集第71巻10号1958頁「ブラウン管事件」)。
また、企業活動に密接に関連する法令の中には、個別の規定で域外適用を認めるものもあり、その例として、個人情報保護法171条は、国内にある者への物品やサービスの提供に関し、国内にある者の個人情報を外国で取り扱う場合に日本法を適用することを定めているほか、知的財産法分野では、令和5年改正不正競争防止法19条の3が、国内事業者が日本国内で管理する営業秘密に対する国外からの侵害行為について、日本の法律の適用を認めています。
属地主義と特許法
特許法についてみると、各国共通の考え方として、その地理的適用範囲は属地主義によって画されるものと解されています。特許法の立法管轄を各国が有することはもちろん、特許権付与の根拠となる特許は国家が主権に基づき行う行政処分に位置付けられるため、特許法は、その適用範囲を自国の領域内にとどめる属地主義の考え方に馴染みやすいといえます。
もっとも、属地主義の具体的な解釈、つまり、どこまで厳格に属地主義を適用するか、は各国によって考え方が異なり、日本は、米国などと比較すると、厳格な適用をしてきたといわれます。
特許独立の原則との関係
属地主義に関連する考え方として、特許独立の原則があります。特許独立の原則とは、特許要件や出願その他の各種手続を各国が定め、例えば、外国のファミリー出願に特許が付与されなかったり、特許が無効化されたりしたとしても、自国の特許の成否や有効性には影響しない、という考え方です。これは、もともと、第一国出願に基づいて他国への出願を認める優先権制度を踏まえて、各国出願や特許の関係を規律する原則で、パリ条約においては、優先権に関する4条の直後の4条の2において、以下のとおり規定されています。
第4条の2(各国の特許の独立)
(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
(2) (1)の規定は,絶対的な意味に,特に,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由についても,また,通常の存続期間についても,独立のものであるという意味に解釈しなければならない。
(3) (1)の規定は,その効力の発生の際に存するすべての特許について適用する。
(4) (1)の規定は,新たに加入する国がある場合には,その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても,同様に適用する。
(5) 優先権の利益によつて取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
属地主義と特許独立の原則の関係については議論があり、特許独立の原則を属地主義の根拠とする考え方が有力といわれますが、実務的観点から比較すると、属地主義は、各国の特許権の効力が及ぶ地理的範囲を限定するものであるのに対し、特許独立の原則は、ある国の特許の消長は他国におけるファミリーの消長に影響されない、ということを定めるものといえます。権利者の立場からは、それぞれ、特許権の地理的射程の問題と、特許性における外国ファミリーからの独立性の問題、と捉えても良いかも知れません。
なお、いわゆる国際消尽の問題に関するBBS事件では、特許権者が外国で販売した製品を日本に並行輸入した場合における日本の特許権の行使の可否が争われ、その際、特許独立の原則や属地主義との関係も議論されました。この点につき、最高裁判所の判決(最三判平成9年7月1日平成7年(オ)第1988号民集51巻6号2299号)は、権利者が海外で特許製品を販売した事実を日本国内の実施行為についてどのように考慮するかは専ら国内法の解釈問題であって、特許独立の原則や属地主義は関係ない、と判示しています。趣旨として、国内の行為に対する国内の権利行使であるため、特許権の地理的射程という観点から渉外的要素はなく、また、製品が販売された外国の特許の効力を問題にするものでもないため、外国ファミリーからの独立を議論する必要もない、と考えれば分かりやすいかもしれません。
属地主義の体系的位置づけ
国際私法の基本的概念
渉外的要素のある事案では、日本に関連がある事件であっても、当然に日本法が適用されることにはなりません。このような場合、まず、どの国や地域の法律を「準拠法」とするか、という問題が生じます。
準拠法は、その適用が問題になる個別の法律関係ごとに決定されますが、その単位となる法律関係は「単位法律関係」と呼ばれ、単位法律関係に適用される法は、実体法と手続法を併せて「実質法」と呼ばれます。
ある単位法律関係に適用される実質法を準拠法として選択する際には、その単位法律関係に特定の地域の実質法を結びつける要素事実を考えることになりますが、そうした要素事実は「連結点」と呼ばれ、また、その連結点に基づく準拠法選択の規範は「抵触法」と呼ばれます。我が国における抵触法の成文法上の法源は、「法の適用に関する通則法」(平成18年法律第78号。以下「通則法」といいます。)で、明治時代に制定された「法例」(明治31年法第10号)という法律を全面改正した法律です。
通則法では、単位法律関係と「最も密接な関係がある地」(「最密接関連地」)を準拠法の原則的な決定基準としつつ、類型化された個々の単位法律関係について、連結点となる事実が定められています。例えば、契約のような法律行為については、当事者の「選択」が連結点となり(同法7条)、法律行為の時点で「選択」がされなければ最密接関連地の法となることが規定されています(同法8条1項)。国際契約では準拠法に関する規定が設けられるのが通例ですが、これは、当事者の「選択」を明示することで、最密接関連地を巡る見解の相違を解消するものといえます。
属地主義の位置付けを巡る議論
以上を踏まえて属地主義と国際私法の関係を考えるに、抵触法は、国境を跨いだ渉外的要素のある法律関係に適用される実質法を決定するものであるのに対し、属地主義は、ある国の特許法は外国の事象には適用されない、という考え方です。そのため、特許権を巡っては、そもそも国境を跨いだ問題が生じず、抵触法など関係ないともいえそうですし、実際、そういった考え方も存在します。
もっとも、経済活動のグローバル化が進むと特許権を巡る法律関係に渉外的要素が入りこむこともあるため、属地主義と国際私法の関係を考える必要があるという考え方が一般的になっており、具体的には、属地主義をもって、①実質法の解釈の中で考慮されるべき原則と解する見解、②抵触法上の原則に位置づける見解、そして、③それらの双方で考慮すべきとする見解があり、さらに、実質法の中で属地主義を考慮する場合には、抵触法の判断が必要かどうかで観点が分かれるといわれます。
カードリーダー事件判決
特許権侵害事件における属地主義の位置付けを示した判決としては、最一判平成14年9月26日平成12年(受)第580号民集56巻7号1551頁「カードリーダー事件」がリーディングケースとされます。同判決は、通則法施行前のもので、事案は、米国企業が有する米国特許権を侵害する製品を日本企業が日本国内で製造し、その米国子会社が米国へ輸入して米国で販売した、というもので、特許権者である米国企業は、日本の製造元に対し、米国特許権に基づく特許権侵害訴訟を、日本の裁判所で提起しました。
この事件で、日本で米国の特許権を行使する根拠となったのは、米国特許法271条(b)項に基づく「誘引侵害」でした。誘引侵害とは、特許権侵害を積極的に誘引した者は、自ら侵害行為をしていなくとも特許権侵害の責任を負う、という制度で、一定の場合に、外国での誘引行為にもこの規定を適用できると解されています。そこで、特許権者は、日本の裁判所で訴えを提起し、日本で米国特許権を侵害する製品を製造し、米国子会社を通じて米国内で販売させるのは、米国特許権の誘引侵害である、と主張したわけです。
とはいえ、日本の特許法に誘引侵害の規定はなく、外国特許法の域外適用を認める規定もありません。そのため、この事件では、日本国内における行為に対し、米国のそういった法律を適用することが可能なのかが争点になりました。
この問題について、カードリーダー事件判決は、差止請求と損害賠償請求とに分けて検討し、まず、差止請求については、単位法律関係を特許権の効力と位置付けた上で、最密接関連地となる登録地法、すなわち米国法が準拠法になるとの考え方を示しました。そうすると、日本国内の行為に誘引侵害が認められる可能性も出てくるのですが、同判決は、準拠法は米国法としながらも、米国特許権に基づく差止請求を認めると米国特許権の効力を日本で認めることになって「我が国の採る属地主義の原則に反する」とし、そのような結果は我が国の公の秩序に反するとして、以下の法例33条に基づき、米国法の適用を否定しました。
第三十三条 外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定ノ適用カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス
次に、損害賠償請求については、当時の法例11条1項が、以下のとおり、原因事実発生地を連結点として準拠法を決定するものとしていたところ、カードリーダー事件判決は、米国で直接侵害行為があったことをもって同国を原因事実発生地とし、米国法が準拠法となるものと判断しました。
第十一条 事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル
(略)
この場合、やはり日本国内の行為に誘引侵害の規定が適用され、被告となった日本企業に損害賠償責任が生じる可能性が生じますが、判決は、さらに、以下の法例11条2項により、日本法を累積的に適用し、結論としては、不法行為についても誘因侵害の規定の適用を排除しました。
第十一条 (略)
2 前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス
(略)
「累積的適用」とは、上の条文にあるように、外国法を準拠法とした場合に不法行為となる場合であっても、日本法を準拠法とすれば不法とはいえない場合には、外国法を適用しない、という考え方です。カードリーダー事件判決は、この規定を前提に、属地主義のもと、誘引侵害を違法とする規定のない日本では被告の行為は違法にならない、として、損害賠償請求も棄却したわけです。
カードリーダー事件判決に見る属地主義の体系的位置付け
カードリーダー事件判決を踏まえて、属地主義の法体系上の位置付けについて考えると、同判決は、差止請求についても、損害賠償請求についても、準拠法の決定をしていますので、特許権侵害に関する法律関係に抵触法の適用がないとする考え方には立っていません。
また、同判決は、抵触法の判断において、差止請求については最密接関連地により、損害賠償請求については法例11条1項により、それぞれ準拠法を決定しており、いずれにおいても属地主義のことは考慮していないため、属地主義を抵触法の中で考慮する見解にも立っていないものと考えられます。
他方、同判決は、差止請求における判断においては、属地主義を理由に米国法の適用が我が国の公序に反するとしてその適用を排斥し、損害賠償請求についても、法の累積的適用に関して属地主義を考慮し、米国法の適用を排除しています。これらのロジックは理解しにくい面もあり、その是非について議論のあるところですが、これまで整理したところによれば、カードリーダー事件判決は、抵触法上の判断が必要であるとの前提に立ちつつも、そこでは属地主義を考えず、実質法上の判断において属地主義を考慮する、という考え方に立つものと思われます。
通則法改正とカードリーダー事件判決との関係
カードリーダー事件判決において適用された法例は、上述のとおり、その後の全面改正によって通則法となっており、不法行為の連結点は、法例11条1項における原因事実発生地から、以下の通則法17条に規定する「加害行為の結果が発生した地」(結果発生地)に変更されています。
(不法行為)
第十七条 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。
カードリーダー事件判決の事案において、どのような事実をもって結果の発生と考えるかは議論の余地もありそうで、特許権侵害においては、現に実施行為が行われることが原因行為であり、かつ、結果の発生でもあると考えるなら、結果発生地は日本になり、特許権者の事業における販売機会の喪失等をもって結果と捉えるなら、米国となりそうです。
もっとも、通則法も、以下の同法22条1項が法の累積的適用を規定しているため、カードリーダー事件判決の考え方を前提にする限り、結果発生地をいずれと考えたとしても、誘引侵害の適用が排斥されることに変わりはなさそうです。
(不法行為についての公序による制限)
第二十二条 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない。
(略)
属地主義と権利一体の原則
権利一体の原則とは
カードリーダー事件判決では、準拠法は米国法とされながら、差止請求については公序を理由に、損害賠償請求については累積的適用を理由に、それぞれ実質法上の適用以前に請求が排斥されました。他方、公序や累積的適用といった問題がない場合には、侵害の成否等、実質法に基づく実体判断が行われることになります。ここで問題になるのは、権利一体の原則です。
「権利一体の原則」(「オール・エレメント・ルール」)とは、特許権侵害が成立するためには、実施行為にかかる製品やサービス等が特許発明のすべての構成要件を充足することが必要であるとする考え方です。伝統的に、特許請求の範囲(クレーム)の役割については、権利の外縁を画するものと捉える「周辺限定主義」と、権利の中心部分を規定するものと捉え、権利の外縁は明細書も検討して判断する「中心限定主義」に分かれるといわれますが、特許請求の範囲によって権利の境界を示す権利一体の原則は、周辺限定主義になじむものといえます。
実施行為主体と権利一体の原則
上述のとおり、権利一体の原則は、特許権侵害が成立するために、実施行為の対象となる製品やサービス等がすべての構成要件を充足することを求めるものですが、これを、行為主体の面から見ると、ある行為主体が特許発明の構成要件のすべてを実施していることを要する、ということを意味します。当然ながら、複数の人が特許発明の一部を別個独立に実施している場合には、それぞれの行為が間接侵害にあたる場合は別段、そうでなければ、単にそれぞれが特許権を侵害しない行為をしていることになるだけで、両者を合わせるとたまたま全構成要件が含まれることになったとしても、それをもって特許権侵害ということはできないからです。
もっとも、複数の人が実施行為の一部を行っているにとどまる場合でも、その間に一定の関連性があり、一体の実施行為といえる場合には、特許権侵害が認められることがあります。類型としては、複数人の間の人的関係に着目する場合(道具理論)と、特定の関与者の実施行為全体への関与の態様に着目する場合(支配管理論)があります。
裁判例として、道具理論については、特許発明にかかる製法の最終ステップが被告からの製品購入者によって実施されていた場合に、その製法により使用されることが当然に予定され、他に用途がない製品であったことから、被告が購入者を道具として最終ステップを実施しているとして特許権侵害を肯定した東京地裁の判決がよく引用されます(東京地判平成13年9月20日平成12年(ワ)第20503号「電着画像の形成方法事件」)。戦前の大審院の時代には、製造委託において、①受託者への工賃の支払い、②委託者による指揮監督、③製品の委託者への全量納品といった条件が満たされている場合に、受託者は物理的に生産を行っていても委託者の手足であって、実施行為の主体は委託者であるとした判決がありますが(大判昭和13年12月22日民集17巻24号2700頁「模様メリヤス事件」)、上記東京地判も、同様の発想に基づくものといえるでしょう。
また、支配管理論については、システムの発明につき、一方が他方の履行補助者となるような人的関係のない、発注者と受注者の双方が実施行為にかかわっている事案において、誰が行為主体といえるかは、構成要件の充足の問題とは別に、誰がシステムを支配管理しているかを判断して決定すべきであるとし、実施行為者はシステムを支配管理している受注者であるとした東京地判平成19年12月14日平成16年(ワ)第25576号「眼鏡レンズの供給システム事件」があります。「支配管理」という言葉は、著作権法の分野で、カラオケ店が客の歌唱行為を管理し、利益を得ていることを根拠に、歌唱行為の主体はカラオケ店であるとした有名な判決(最三判昭和63年3月15日昭和59年(オ)第1204号民集42巻3号199頁「クラブキャッツアイ事件」)を彷彿とさせますが、いずれも、行為主体を、物理的な行為からでなく、規範的観点から判断する点で共通するものといえます。
権利一体の原則と属地主義
以上説明してきた権利一体の原則に属地主義をあてはめると、特許権侵害が成立するためには、特許権の存する国において、特定の行為者が、特許発明の構成要件の全部について実施行為をしていることが求められることになります。
これが問題になる状況を具体的にみると、一般的な工業製品にかかる物の発明については、たとえサプライチェーンがグローバルに展開され、部材は世界各地で調達されていても、最終的に実施品が製造・販売される時点では、その場所が特定されます。そのため、最終的にすべての構成要件を充足する製品が国内で製造または販売されていれば、外国法を国内で域外適用をしようとするのでない限り、権利一体の原則との関係で属地主義は問題にならないのが通常です。これは、物の発明は物の静的な構造や特性に着目するものであって、通常、その構成を観察する時点でその所在地は特定の場所に定まるからです。
他方、手順(ステップ)といった機能的・動的要素により、発明の構成が経時的に表現されることの多い方法や製法の発明については、そのプロセスの一部が海外で行われることもあり得るため、属地主義の問題が顕在化しやすいといえます。上に紹介した電着画像の形成方法事件でも、最終ステップを実施する購入者の一部は海外所在であったため、属地主義との関係が議論されることになりましたが、判決は、「国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできない。」として、海外への輸出行為について侵害を否定しています。この判決は、上述のとおり、国内販売分については、道具理論に基づいて侵害を肯定していますので、実施行為が複数人に分散している点については規範的にひとりの行為者による行為と判断する一方で、行為地の問題については、あくまで物理的な場所を問題にし、属地主義を厳格に適用したものといえます。
均等侵害との関係
我が国の裁判例は、均等侵害の判断において、発明を上位概念化することにより、特許発明の構成のうち、従来技術との関係で非本質的といえる部分を捨象した上で属否の判断を行う、という考え方を採用しています。これは、構成要件ごと(element by element)の判断から離れた手法で、個々の構成要件の充足は求めないため、本来的意味での権利一体の原則とは異なる判断様式ともいえます。
もっとも、属地主義は、侵害を構成するとされた実施行為の全部が日本国内で実施されることを求めるもので、それが文言侵害を構成する行為であっても、均等侵害を構成する行為であっても、適用関係に相違は生じないと思われます。
ネットワーク関連発明を巡る問題
問題の所在
ネットワーク関連発明とは、ネットワークと、ネットワークを介して接続されたサーバやクライアント等、複数のコンピュータを組み合せたシステムによって実施される発明をいいます。実際の構成として、あるシステムを構成する要素はひとつの国で完結しているとは限らず、また、こういった発明を用いたサービスは、多くの場合、そのサーバの物理的な場所に関係なく世界各地の利用者がそれぞれの端末上で利用することができます。
こういった特性から、ネットワーク関連発明は、①構成と②効果のそれぞれの面から、属地主義との関係で問題を生じやすくなると考えられます。
まず、上記①の構成面の問題は、ネットワーク関連発明においては、システムというひとつの「物」が同時に国境を跨いで存在し得るため、必ずしもひとつの国の特許で実施品の全体を捕捉できないという点にあります。その背景として、システムは、物の発明であっても、しばしば処理ステップで構成が表現され、機能的・動的要素によって特定されることが指摘できます。もちろん、最終的には、機能的記載から機能に対応する構造等が特定される必要はあるのですが(実用新案審査基準第Ⅱ部第2章第3節4.1、同第Ⅲ部第2章第4節2.1等。米国におけるmeans plus function claimに関する議論も同様の問題意識といえるでしょう。)、個別の処理が各国で行われる場合には、特定された物(システム)が複数国に存在し得るわけです。
これは、ひとつの物を静的に観察する際には1か所にしか存在できない、という通常の物とは異なる特性であり、この点で、ネットワーク関連発明は、属地主義の問題から逃れられないことになります。発明が正面から動的要素で特定される方法の発明として構成された場合には、この点がより顕著になるでしょう。
次に、上記②の効果面の問題は、ネットワーク関連発明においては、国境を跨いだ分散システムかどうかにかかわらず、しばしば、サーバ等の構成要素の所在に技術的意味がなく、それがどこにあろうと、利用者に同一のサービスを提供できる、という点にあります。こういった特性から、一定の場所に結び付けられる発明でない限り、ある国に障害となる特許がある場合、当該国に同一のサービスを継続的に提供しながら、特許のない国にサーバを設置することができます。こういった効果面の特性も、属地主義との緊張関係を生みます。
このように、ネットワーク関連発明は、①構成の面でひとつの物が国境を跨いで同時に存在し得ること、そして、②効果の面で所在場所に技術的意味がないことから、属地主義とは常に緊張関係を孕む発明類型になるのです。
その対策として、権利者としては、国内の端末における処理で発明を構成したり、サーバを構成要件外のサブコンビネーションとして組み合せるサブコンビネーション発明としたりするなど、クレームドラフティングにおける工夫もされてきたと理解しています。しかし、ネットワーク関連発明の内容は、常に端末側で捕捉できるものとは限らないことや、システム設計の柔軟性の高さを考えると、クレームドラフティングによる対応には本質的な限界があります。そのため、法解釈において、サーバの所在に捉われずに特許権を行使できないかが問題になります。
裁判例
こういった問題に関し、今回紹介する事件とその関連事件以前の裁判例として、知財高判平成22年3月24日平成20年(ネ)第10085号「インターネットナンバー事件」は、韓国にサーバが設置されていた事案で日本の特許権の侵害を認め、そのサーバの除却を命じています。しかし、この事件では、属地主義の適用関係は争点になっておらず、この点について裁判所の判断は示されていません。
米国の裁判例としては、メール配信システムにかかる米国特許権をサーバの一部が海外にあるシステムについて行使した事案において、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、無線送信サーバは海外にあったものの他の被告のシステムは全て米国内に存在し、配信サーバを含む全ての装置は、全て米国で制御が可能であったこと、そして、被告システムの使用による利益は米国内で享受することができることを理由に、侵害を肯定しています(NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005))。
法改正を巡る議論
立法動向としては、産業構造審議会知的財産分科会の第49回特許制度小委員会(令和6年11月6日)でこの問題が取り上げられ、調査研究やヒアリングの結果、「実施の『一部』が国内(発明の構成要件の一部が国外)である場合に、発明の『技術的効果』及び『経済的効果』が国内で発現していることを要件として、実質的に国内における行為と認められる(=日本の特許権の効力が及ぶ)ことを明文化する意義について、おおむねコンセンサスが形成された」と報告されるとともに、具体的な規定のあり方に関し、3つの「方向性案」が示されています(特許庁「特許制度等に関する検討課題について」16頁)。
事案の概要
事案
本件は、日本の利用者向けに動画配信を行う企業間の特許権侵害訴訟で、一審原告・被上告人は日本の株式会社(株式会社ドワンゴ)、一審被告・上告人は米国ネバダ州の外国法人(FC2, Inc.)外1社です。
一審原告・被上告人は、発明の名称を「コメント配信システム」とするシステムの発明にかかる特許(特許第6526304号)を有していました。同発明は、動画及び動画に対してユーザが書き込んだコメントを表示する端末装置と、当該端末装置に当該動画や当該コメントに係る情報を送信するサーバとをネットワークを介して接続したシステムに関するもので、動画上に表示されるコメント同士が重ならないように調整するなどの処理を行うことにより、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上を図るものでした。
他方、一審被告・上告人は、米国内で、ウェブサーバ、コメント配信用サーバ及び動画配信用サーバを設置管理し、日本の利用者に向けて複数の動画共有サービスを提供していたところ、それらのサービスは、動画の再生に併せてユーザによって書き込まれたコメントが表示されるものとなっていました。
そこで、一審原告・被上告人が、上記特許にかかる特許権(「本件特許権」)に基づき、一審被告・上告人に対し、日本で特許権侵害訴訟を提起したのが本件訴訟です。一審原告・被上告人が主張した、侵害にかかる実施行為の内容は、日本の利用者が動画を視聴する際に、インターネットを介して、一審被告・上告人のウェブサーバから利用者の端末にHTMLファイルとJavaScriptファイルが配信されることにより、随時発明にかかるシステムが「生産」されるというものでした。
発明の構成や被告の実施行為等、事案のより詳細な内容については、原判決の解説「動画配信システムにおけるサーバが日本国外に設置されていた場合において特許権侵害の成立を認めた知財高裁大合議事件判決について」や、第一審の判決の解説「被告の動画配信システムにおけるサーバが日本国外に設置されていた場合において特許権侵害の成立を否定した東京地裁判決について」をご覧いただければと思いますが、今回紹介する最高裁判所の判決は、理由中で以下のとおり事実関係を整理しており、これを基礎に判断を示しています。
上告人は、本件各サービスを提供するため、米国内で、ウェブサーバ、コメント配信用サーバ及び動画配信用サーバを設置管理しているところ(ただし、一部のサービスに係る動画配信用サーバは、第三者が設置管理するものであり、我が国に所在する場合と所在しない場合があり得る。)、そのうちのウェブサーバから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我が国所在の端末に対し、HTMLファイル及びプログラムを格納したファイル(JavaScriptファイルなど)を配信している(以下、この配信を「本件配信」という。)。
本件配信は、ユーザが、我が国所在の端末を使用し、本件各サービスに係る動画を視聴するための各ウェブページ(以下「本件各ページ」という。)にアクセスすると、前記プログラムを格納したファイル等を米国所在の前記ウェブサーバから送信し、当該端末にダウンロードさせるものである。
本件配信がされると、前記端末は、前記ファイルの記述に基づき自動的に(ただし、動画再生ボタンの押下を要する場合がある。)、インターネットを介して接続された前記動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバにそれぞれ動画及びコメントに係るデータファイルを要求し、これらのファイルを受信してコメント同士が重ならないように調整した上、動画にコメントを重ねて前記端末上で表示するなどの処理を行うことになり、前記端末と前記動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとを含む本件各発明の技術的範囲に属するシステム(以下「本件システム」という。)が構築される。
なお、問題になった事実をカードリーダー事件と比較すると、同事件では、上述のとおり、米国での直接侵害を日本で誘引する行為を対象に、米国特許法に基づく訴訟が日本で提起されたものであるのに対し、本件では、実施行為の一部が米国のサーバで行われている場合に、日本の特許法に基づいて日本で侵害訴訟が提起された、という点で異なります。
第一審判決
この事案において、第一審の東京地方裁判所の判決(東京地判令和4年3月24日令和元年(ワ)第25152号特許権侵害差止等請求事件)は、まず、準拠法につき、差止等の請求については登録地法により、また、損害賠償請求については、通則法17条により、それぞれ日本法が準拠法となるとしました。上述のとおり、通則法17条は、不法行為について、「加害行為の結果が発生した地の法」を準拠法とするものですが、一審判決は、日本の特許権の侵害が認められるのであれば、財産権侵害という結果の発生地は日本であるとの考え方に立っています。
その上で、一審判決は、サーバが海外にあることから、国内において「生産」が行われているとは認められないと判断し、原告の請求をいずれも棄却しました。
原判決
知的財産高等裁判所は、特別部による判決(知財高判令和5年5月26日令和4年(ネ)第10046号特許権侵害差止等請求控訴事件)において、東京地方裁判所の上記判決を覆し、一審原告の請求を一部認容しました。これが、今回紹介する最高裁判決の原判決にあたります。
原判決は、まず、準拠法について、一審判決を基本的に維持し、差止等の請求についても、損害賠償請求についても、日本法が準拠法となるとしました。
その上で、実質法上の判断としては、「ネットワーク型システム」の語を「インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム」と定義した上で、下記のとおり述べ、構成要素となるサーバが国外にある場合であっても、次の各点を総合考慮して、問題となる行為が日本の領域内で行われたものとみることができるときは、システムの「生産」に該当する、との考え方を示しました。
- 行為の具体的態様
- システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割
- システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所
- その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響
- 等
ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。
また、原判決は、上記考慮要素へのあてはめを以下のように行い、結論として、「生産」該当性を肯定しています。
これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。
次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人FC2のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。
さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明1との関係で、特許法2条3項1号の「生産」に該当するものと認められる。
この原判決に対する上告審の判決が、今回紹介する判決です。
判旨
属地主義とネットワーク関連発明の関係
判決は、まず、以下のとおり、カードリーダー事件判決を引用し、属地主義のもと、我が国の特許権の効力はその領域内においてのみ認められるものであることを踏まえつつ、ネットワーク関連発明において、システムの一部が海外にあることを理由に実施行為を否定したのでは、特許法の目的に沿わないと述べました。
我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められるが(最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照)、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、当該システムを構築するための行為が特許法2条3項1号にいう「生産」に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。
また、判決は、これを受けて、以下のとおり、システムの一部が海外にある場合であっても、「システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における『生産』に当たると評価されるとき」は、我が国の特許権の効力を及ぼし得るものとしました。
そうすると、そのような場合であっても、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における「生産」に当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。
あてはめ
次に、本件へのあてはめにあたり、判決は、以下のとおり、本件システムの特徴につき、「本件配信による本件システムの構築は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、その結果、本件システムにおいて、コメント同士が重ならないように調整するなどの処理がされることとなり、当該処理の結果が、本件システムを構成する我が国所在の端末上に表示されるものである」ことを指摘しました。
本件配信は、プログラムを格納したファイル等を我が国の領域外のウェブサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受信させるものであって、外形的には、本件システムを構築するための行為の一部が我が国の領域外にあるといえるものであり、また、本件配信の結果として構築される本件システムの一部であるコメント配信用サーバは我が国の領域外に所在するものである。しかし、本件システムを構築するための行為及び本件システムを全体としてみると、本件配信による本件システムの構築は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、その結果、本件システムにおいて、コメント同士が重ならないように調整するなどの処理がされることとなり、当該処理の結果が、本件システムを構成する我が国所在の端末上に表示されるものである。
その上で、判決は、以下のとおり、本件システムの構築は国内の端末で発明の効果を当然に奏させるようにするもので、そのこととの関係でサーバが海外にあることに特段の意味はないこと、そして、本件システムが特許権者に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もないこと、の2点に言及し、実質的に日本国内で本件システムの「生産」が行われていると評価するのが相当であるとしました。
これらのことからすると、本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によるものである本件配信やその結果として構築される本件システムが、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人は、本件配信及びその結果としての本件システムの構築によって、実質的に我が国の領域内において、本件システムを生産していると評価するのが相当である。
上記判断のもと、判決は、本件配信による本件システムの構築は、特許法上の「生産」に該当するとし、結論として、上告を棄却しました。
関連事件について
本件の当事者間には、上述のとおり、今回紹介した事案とは別に、本件特許のファミリーである特許第4734471号及び第4695583号にかかる特許権の侵害訴訟も係属していました。この事件では、海外のサーバからのプログラムの配信が、特許法2条3項1号にいう「提供」にあたるかが主たる争点となりましたが、原判決(知財高判令和4年7月20日平成30年(ネ)第10077号特許権侵害差止等請求控訴事件)は、以下のとおり述べ、これを肯定していました(この判決の解説は、こちらをご覧ください。)。
本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって(略)、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明1-9及び10に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明1-9及び10の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。
この件における最高裁判所の判決(最二判令和7年3月3日令和5年(受)第14号、第15号特許権侵害差止請求事件)は、まず、以下のとおり述べ、「問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における『電気通信回線を通じた提供』に当たると評価されるときは、当該行為に我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はない」としました。
我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められるが(最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照)、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合に、我が国の領域外からの送信であることの一事をもって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、上記の提供が「電気通信回線を通じた提供」(特許法2条3項1号)に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における「電気通信回線を通じた提供」に当たると評価されるときは、当該行為に我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。そして、この理は、特許法101条1号にいう「譲渡等」に関しても異なるところはないと解される。
その上で、同判決は、以下のとおり述べ、「上告人らは、本件配信によって、実質的に我が国の領域内において、本件各プログラムの電気通信回線を通じた提供をしていると評価するのが相当である。」としました。
本件配信は、本件各プログラムに係るファイルを我が国の領域外のサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受信させるものであって、外形的には、その行為の一部が我が国の領域外にあるといえる。しかし、これを全体としてみると、本件配信は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、本件各サービスは、本件配信により当該端末にインストールされた本件各プログラムを利用することにより、ユーザに、我が国所在の端末上で動画の表示範囲とコメントの表示範囲の調整等がされた動画を視聴させるものである。これらのことからすると、本件配信は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程として行われ、我が国所在の端末において、本件各プログラム発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によりされるものである本件配信が、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人らは、本件配信によって、実質的に我が国の領域内において、本件各プログラムの電気通信回線を通じた提供をしていると評価するのが相当である。
このように、判断に用いられたロジックは、2件の最高裁判決で基本的に共通するものといえます。
コメント
判決の意義と射程について
判決は、ネットワーク関連発明の特質を踏まえ、サーバの一部が海外にあったとしても、問題となる行為を全体としてみたときに、当該行為が実質的に我が国の領域内における実施行為にあたると評価される場合には我が国の特許権の効力が及ぶ、との考え方を示しました。最高裁判所が、属地主義との関係で、サーバの一部が外国にある場合にも国内の行為と同視できることを明確に示したことには、大きな意義があると思われます。
判決の射程については、判断の前提が「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合」(関連事件判決では「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合」)とされていることから、基本的に、ネットワーク関連発明のみを対象としたもので、属地主義を緩和する考え方が直ちに他の技術分野に及ぶものではないと思われます。
準拠法について
知財高裁の判決で検討されていた準拠法の問題について、今回の判決 は、属地主義の問題の文脈でカードリーダー事件判決を引用しているものの、個別的な検討対象としていません。趣旨としては、カードリーダー事件判決に基づき、属地主義を実質法上の問題に位置付けてこれを判断の対象とする一方、前提となる抵触法の問題については、差止請求についても、損害賠償請求についても、特に問題なく日本法を準拠法とすることができることから言及していないものと思われます。
判断内容について
属地主義に関する判断内容についてみると、上述のとおり、知財高裁の判決は、問題となる行為が日本の領域内で行われたものとみることができるかを諸事情の総合考慮によって判断するという考え方を示すとともに、そこで考慮要素となる事実を列挙していました。これに対し、最判は、単に「全体としてみたときに」「実質的に」という形で領域内の実施行為といえるかを判断すべきとするのみで、考慮すべき要素を含めて規範化することはしていません。そのため、知財高裁の判決と比較して、事例判断としての性質が強くなったものと考えられます。
次に、領域内の実施行為といえるかの判断において考慮された事実についてみると、判決は、上述のとおり、①発明の効果を奏する上で、サーバの所在地に特段の意味がないことと、②特許権者に経済的な影響を及ぼさないというべき事情がないこと、の2点に着目しています。これらの関係として、上記②の点につき、「経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない」との消極的な表現が用いられていることに鑑みると、判決が主要な考慮要素に位置づけるのは、①発明の効果との関係でサーバの所在に意味がない、という点で、②の経済的影響は、たとえ①の点が認められるとしても、サーバが外国にあることで、特許権者に対して経済的な影響を及ぼさない場合には、領域内の行為であることを否定し、または、否定する方向に働く、という、例外事情に位置付けられたものと考えられます。
各要素の内容としては、上記①は発明の技術的効果に着目するものであり、②は経済的効果に着目するものといえます。その意味では、いずれも、実施行為の効果を基礎に日本法の適用の基礎とする面があり、法の地理的適用範囲との関係では、効果主義に近づく面があるといえそうです。
今後の実務への影響ですが、判決は、上述のとおり、上記2点の考慮要素を、日本の特許権の効力が及ぶ範囲を画する基準には位置付けず、事例判断における考慮要素とするにとどめています。これは、動きの速い技術分野において判断基準を固定することを避ける意図があるのかも知れませんが、適用対象をネットワーク関連発明に限定する限り、これら2点によって判断を行うことには合理性があると思われるため、当面の実務では、事実上の判断基準として機能していくことになるのではないかと感じられます。
なお、ある製品やサービスが特許発明の構成要件を充足するかを考えるにあたり、効果をどのように考慮するかが問題になることがありますが、ここで問題になっているのは実施行為の成否で、実施品の属否は構成によることが前提です。つまり、属否の判断は構成によりつつ、ネットワーク関連発明における行為地の判断においては効果も考慮する、というのが今回の判決の整理になると考えられます。
法改正との関係について
上述のとおり、ネットワーク関連発明と属地主義の問題を巡っては、現在、産業構造審議会知的財産分科会の特許制度小委員会において法改正の議論が進められており、実施行為の一部が国内にあることと、発明の技術的効果及び経済的効果が国内で発現することを要件に、日本法の適用を認めることが提案されています。これに対し、今回の判決は、実施行為の一部が国内にあるかどうかは問題にしていません。
産業構造審議会において一部国内実施を要件とすることが提案されているのは、属地主義を過度に緩和することで、国家間の礼譲(comity)の問題のほか、権利範囲の拡大に伴う不当な権利行使や過剰なクリアランス負担といった問題を回避することが目的と思われます。別途国際管轄の問題はあるものの、カードリーダー事件判決にいう「我が国の採る属地主義の原則」という言葉は日本国内における外国特許権の効力にも適用され得ることからすると、属地主義の緩和は、日本国内における外国特許権の効力の承認にも繋がりかねません。一部国内実施要件は、こういった問題を回避する上で、技術的効果や経済的効果といった効果面に加え、構成面でも一定の要件を課そうとするものと思われます。
しかし、今回の判決も述べているとおり、国内における技術的効果の発現がサーバの所在によって影響を受けないことがネットワーク関連発明を巡る議論の出発点ですので、対応の方向性としては、物理的なサーバの所在から離れ、規範的観点から実施行為の場所を捉えるようにすべきものと考えられます。技術的効果や規範的効果を考慮するのも、行為地の規範的把握が目的と思われますので、あえて物理的な行為地を問題にする一部国内実施を要件とすることには疑問なしとしません。問題の原点に立ち返れば、端的に、日本に技術的効果が発現しており、そのことがサーバの所在に影響されないという点を要件とすれば足りるのではないかと感じられます。
また、そのような条件を満たしながら経済的効果がない場合には、日本法適用を否定することも適切な限定になると思われますが、特許権侵害に基づく損害は、侵害者の収益ではなく、特許権者の逸失利益という消極損害をその内容とするため、サーバ内の処理のみを対象にする発明などは別段、国内法適用が問題となる事案では、多くの場合、技術的効果を得られる場所で損害、すなわち、経済的効果も生じ、経済的効果の実質的意味は、多分に技術的効果と重なるように思われます。そのため、経済的効果が生じないことをもって、技術的効果が認められる場合の例外に位置づける判決の発想は、立法論にもなじむのではないかと思われます。
個人的には、これらによって適切な要件を定立できるのではないかと思われますが、さらに限定を加えるとするならば、ネットワーク関連発明においては物理的な行為地が意味を持たない、ということを技術内容から表現する意味で、例えば、適用対象を、上に述べたような、ネットワーク関連発明における構成面や効果面での特性を備える発明類型に限定するという方向もあるのではないでしょうか。これならば、一部国内実施要件よりも立法事実に整合的な法改正となり、また、本来属地主義を緩和する必要のない技術分野に改正法が適用される危惧もなくなりそうです。
最後に、そもそも、この問題は法改正によって解決されるべきことか、あるいは、今がその時期か、ということも慎重に考える必要があるように思われます。今回の判決は、上述のとおり事例判断的性格が強く、具体的な規範定立まではしていませんが、半面で柔軟性もあり、また、①発明の効果を奏する上で、サーバの所在地に特段の意味がないことと、②特許権者に経済的な影響を及ぼさないというべき事情がないこと、の2点は、当面の技術状況を前提に日本法の適用可否を判断する上で、一応十分な実務上の指針を示すものになっていると思われます。そのような状況にあっては、すぐに立法を重ねるよりも、まずはこの判決のもとで運用を重ね、解釈による運用の限界や今後発生する問題を見極めた上で立法の方向性を検討していくことも、合理的な選択肢になり得ると感じられます。
本記事に関するお問い合わせはこちらから。
(文責・飯島)