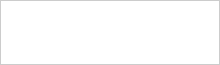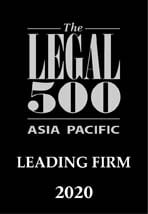2025年3月、経済産業省が公表している営業秘密管理指針が改訂されました。
2025年3月、経済産業省が公表している営業秘密管理指針が改訂されました。
営業秘密管理指針は、不正競争防止法における営業秘密の定義等についての考え方を示すものであり、企業の営業秘密が法的保護を受けられるかどうかの判断において実務の参考にされています。
今回の改訂では、営業秘密を取り巻く環境の変化や、不正競争防止法の見直し、裁判例の動向等を踏まえた加筆や修正が行われており、実務上も把握をしておく必要があると思われるため紹介いたします。
ポイント
骨子
- 営業秘密管理指針とは、営業秘密の定義等(不正競争防止法による保護を受けるための要件など)について、イノベーションの推進、勤務・労働形態の変化、海外の動向や国内外の裁判例等を踏まえて、一つの考え方を示すものであり、平成15年に制定されました。令和7年3月、営業秘密を取り巻く環境の変化に伴う修正と、関連する法制度の見直し、裁判例の動向を踏まえた修正を目的として改訂が行われました。
- 「総説」の項目では、営業秘密と民事措置・刑事罰との関係明確化が図られるとともに、営業秘密以外での情報の保護についての記載と、指針の対象となる事業者の明確化がされました。
- 「秘密管理性について」については、従前の指針において要求されていた秘密情報とそれ以外の情報との「合理的区分」を「必要な秘密管理措置の程度」を判断する要素の1つに位置付けて整理し直すとともに、昨今の企業の情報管理の在り方の変化や裁判例も踏まえて具体例の追加や考え方の整理がされています。
- 「有用性の考え方」については、昨今の裁判例を踏まえて、当該情報が、営業秘密を保有する事業者の事業活動に使用・利用されているのであれば、当該情報が公序良俗に反するなど保護の相当性を欠くような場合でない限り有用性の要件は充足されること、当該情報を不正に取得した者がそれを有効に活用できるかどうかにより認定が左右されないことが確認されています。
- 「非公知性の考え方」については、昨今の裁判例や技術動向を踏まえ、ダークウェブ上に秘密情報が公開された場合の考え方、特許法29条2項との関係及びリバースエンジニアリングによって営業秘密を抽出できる場合の考え方を整理しています。
解説
不正競争防止法による営業秘密保護制度と営業秘密管理指針
不正競争防止法による営業秘密保護制度
不正競争防止法では、営業秘密を不正に取得する行為等を「不正競争」として定義し、民事上の差止による救済(法3条)及び行為者に故意または過失がある場合には損害賠償請求による救済(法4条)を認めています。
具体的には、①営業秘密保有者から不正な手段で営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用、開示する行為(法2条1項4号)、②営業秘密保有者から正当に示された営業秘密を不正に使用、開示する行為(法2条1項7号)、③悪意または重過失により知らないで取得した営業秘密を使用、開示する行為(法2条1項5号、8号)、④善意で取得した営業秘密を悪意で使用、開示する行為(法2条1項6号、9号)、及び⑤営業秘密の不正使用により生じたものを譲渡する行為(法2条1項10号)が民事的な救済の対象となります。
また、不正の利益を得る目的で、またその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、営業秘密を領得、使用等する行為は営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となります(法21条2項)。
不正競争防止法で保護される営業秘密は、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています(法2条6項)。すなわち、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、及び③公然と知られていないこと(非公知性)の3つが同法で保護されるための秘密情報と認められるための要件となります。
営業秘密管理指針とは
営業秘密管理指針(以下「指針」といいます。)は、企業実務において課題となってきた営業秘密の定義等(不正競争防止法による保護を受けるための要件など)について、イノベーションの推進、勤務・労働形態の変化、海外の動向や国内外の裁判例等を踏まえて、一つの考え方を示すものであり、平成15年に制定されました。
指針は法的拘束力を持つものではなく、個別事案の解決は、最終的には、裁判所において、個別の具体的状況に応じ、他の考慮事項とともに総合的に判断されるものですが、企業の秘密管理のミニマムの体制を考えるにあたり参考になるものといえます。
なお、企業の秘密情報の保護に関しては、「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値の向上に向けて」も公表されています。こちらは、秘密情報の漏えいを未然に防ぐための対策例を紹介するものであり、指針とは目的が異なります。
改訂内容
改訂の概要
指針は制定後7回改訂がされており、令和7年3月の改訂が最新の改訂になります。
今回の改訂の背景・方向性は、営業秘密を取り巻く環境の変化に伴う修正と、関連する法制度の見直し、裁判例の動向を踏まえた修正と説明されており、改訂箇所及びその概要は以下のとおりです(以下改訂後の指針を「改訂指針」といいます。)。
| 項目 | 改訂箇所 | 内容 |
|---|---|---|
| はじめに | 改訂の経緯 | ・限定提供データと営業秘密との関係を整理 ・今般の指針改訂の背景の記載 |
| 指針で示す管理水準等 | 指針の位置付けの整理 | |
| 総説 | 営業秘密と民事措置・刑事罰との関係 | 営業秘密の要件についての民事・刑事の整理 |
| 営業秘密以外での情報の保護について | 不正競争防止法改正及び裁判例の動向を踏まえた変更 | |
| 営業秘密以外での情報の保護について>事業者の範囲(新設) | 指針の対象となる事業者の明確化 | |
| 秘密管理性について | 秘密管理性の要件の趣旨 | 秘密管理の対象者の明確化 |
| 必要な秘密管理措置の程度(秘密管理措置の対象者) | 秘密管理措置の対象者の認識についての追記 | |
| 必要な秘密管理措置の程度(合理的区分) | 削除(「秘密管理措置の程度」に合理的区分を含めた考え方を入れ込む) | |
| 必要な秘密管理措置の程度(秘密管理措置の程度) | ・参考裁判例の追加 ・媒体別の考え方の整理 ・社内の複数箇所で情報を共有する場合の考え方の整理 ・生成AIにおいて秘密情報が生成・出力された場合の考え方 |
|
| 有用性の考え方 | 有用性の充足について | 裁判例の考え方を踏まえた追記 |
| 有用性の判断について | 裁判例の考え方を踏まえた追記 | |
| 非公知性の考え方 | ダークウェブに公表された場合について(新設) | ダークウェブ上に営業秘密が公表された場合の考え方を追記 |
| 公知情報の組み合わせ | 裁判例の考え方を踏まえた追記 | |
| 進歩性との関係(新設) | 進歩性(特許法29条2項)との関係の整理 | |
| リバースエンジニアリング(新設) | リバースエンジニアリングにより営業秘密が取得された場合の考え方を追記 |
「はじめに」の改訂内容
「はじめに」の項目では、平成30年の法改正で導入された限定提供データの保護と営業秘密との関係が追記されています。令和6年の法改正により、限定提供データからは営業秘密が除外される形で整理がされています。
また、改訂指針では、指針は、営業秘密企業などが保有する多様な情報のうち、不正競争防止法の営業秘密としての法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すものであり、情報の漏洩防止ないし漏洩対策は「秘密情報の保護ハンドブック」に掲載されていること、限定提供データについては、「限定提供データに関する指針」に掲載されていることを追記しています。
「総説」の改訂内容
「総説」の項目では、営業秘密と民事措置・刑事罰との関係明確化が図られるとともに、営業秘密以外での情報の保護についての記載と、指針の対象となる事業者の明確化がされました。
前述のとおり、不正競争防止法では、営業秘密の領得行為等は、「不正競争」として民事上の差止や損害賠償の対象となるとともに、刑法犯である営業秘密侵害罪が成立する場合があります。
指針の改訂では、最近の裁判例の考え方も引用の上、営業秘密と認められるための3要件は、民事上、刑事上ともに異ならないことを明確にしました。
次に、不正競争防止法上に規定された営業秘密保護制度以外の情報の法律上の保護について法改正等を踏まえて追記をしています。
具体的には、平成30年の不正競争防止法改正で新設された限定提供データ(法2条7項)の保護の条項に基づき、限定提供データに該当するデータが不正取得等された場合には、差止等の民事上の救済を受けられること、営業秘密及び限定提供データのいずれにも該当しない場合でも、不法行為に基づく損害賠償請求の対象となり得ることが明示されました。
指針の対象となる事業者については、項目が新設され、大学や研究機関も指針の対象となることを確認しています。
「秘密管理性について」の改訂内容
秘密管理性は、裁判所が営業秘密該当性を検討するに当たって最も問題となる要件であり、今回の指針の改訂でも多くの箇所に追記、修正が加えられています。
以下では項目毎にその概要を説明します。
■ 秘密管理性の要件の趣旨、秘密管理措置の対象者
秘密管理性の要件は、当該情報が秘密として管理しようとしていることを明確化されることによって、従業員等の予見可能性、ひいては、経済活動の安定性を確保することにあるとされています。
この秘密管理措置を講ずる対象につき、改訂前の指針では「従業員等」とされていましたが、今般の改訂では、従業員等には派遣社員のほか、役員、取引相手先などが含まれることが明記されました。
また、近時の裁判例の考え方を踏まえて、秘密管理性は、従業員全体の認識可能性も含めて客観的観点から定めるべきものであり、従業員個々が実際にどのような認識であったか否かに影響されるものではないとしています。
■ 必要な秘密管理措置の程度
秘密管理性の判断においては、秘密管理措置として合理的区分が要求されていました。改訂前の指針では、「合理的区分」と「その他秘密管理措置」の2つの見出しがあり、「合理的区分」として対象情報(営業秘密)の一般情報(営業秘密ではない情報)からの合理的区分が独立の要件として必要であるようにも読めました。
しかしながら、前述のように秘密管理性の要件が従業員の予見可能性確保のためにあることからすると、合理的区分は秘密管理性を認めるための独立の要件であると解するのではなく、秘密管理性を判断するための一要素と位置付けるのが正確であるといえます。
今回の指針の改訂では、「合理的区分」の見出しを削除し、秘密管理措置の項目の中で、他の情報との分別管理を秘密管理措置の程度を判断するための1つの考慮要素として位置付ける形に整理されています。
また、情報の性質と秘密管理措置の関係についても具体例が示され、以下のように述べて、重要であることが明らかな情報については、IDパスワードの設定程度の技術的な管理措置と、就業規則や誓約書において当該情報の漏えいを禁止するといった「規範的な管理措置」で足りる場合があることが確認されています。
➢ 例えば、情報の性質に関して、当該営業秘密保有者にとって重要な情報であり、当然に秘密として管理しなければなら ないことが従業員にとって明らかな場合には、そうした従業員の認識を活用した管理が許されて然るべきであり、会社のパソコン等へログインするためのIDやパスワードなどにより秘密情報へのアクセスが制限されているといった程度の技術的な管理措置や、就業規則や誓約書において当該情報の漏えいを禁止しているといった規範的な管理措置で足りる場合もある。
➢ 当該媒体に接触する者の限定に関して、従業員ごとに厳密に業務の必要性を考慮した上で限定することまでは求められるものではなく、業務上の必要性等から特定の部署で広くアクセス権限が付与されていたとしても、特定の従業員に限定されていたことに変わりはないと考えられる。
必要な秘密管理措置の程度としては、秘密管理措置の対象者として、①従業員及び役員に向けたものと②取引先に向けたものに分けて整理がされました。取引相手先に向けたものとしては、従業員に向けた秘密管理措置に加えて、当該取引先と秘密保持契約を締結した上で秘密情報を提供したかどうかがポイントとなるとしています。
その他、秘密管理措置に関する参考裁判例も複数追加されています。
■ 秘密管理措置の具体例
秘密管理措置の具体例の項目では、指針は、①紙媒体の場合、②電子媒体の場合、③物件に秘密情報が化体している場合、及び、④媒体が利用されない場合に分けて具体的な秘密管理措置の例を挙げています。
このうち、②電子媒体の場合の秘密管理措置に関して、改訂指針では、外部のクラウドを利用して営業秘密を保管・管理する場合において、情報の内容・性質等からいって、当該営業秘密保有者にとって重要な情報であることが明らかな場合には、外部のクラウドにアクセスするためにID・パスワードなどが設定されているといった程度の技術的な管理措置や、就業規則や誓約書において当該情報の漏えいを禁止しているといった規範的な管理措置で足りる場合もある旨が追記されました。これは、近年の企業の情報管理方法の変化(クラウド利用の普及)に伴い確認された事項です。
■ 営業秘密を企業内外で共有する場合の秘密管理性の考え方
上記項目では、企業内(支店、営業所等)、企業外(子会社、関連会社、取引先、業務委託先、フランチャイジー等)と営業秘密を共有する場合においての秘密管理性の考え方を整理しています。
このうち、改訂指針では、社内の複数箇所で同じ情報を保有しているケースにおいて、昨今の生成AIの利用の普及を踏まえて、AI生成物として秘密情報が出力された場合の秘密管理性の考え方を次のように整理しています。
ここでは、同一企業の管理単位(事業所等)で秘密管理されている情報を生成AIに利用していた場合において、当該管理単位あるいは別の管理単位においてAI生成物として出力されることがあったとしても、その一事をもって秘密管理性が否定されるものではないとしています。
管理単位Cで秘密管理されている情報αを生成AIに利用していた場合であって、その後、管理単位Cで当該生成AIから当該情報αがAI生成物として生成・出力されることがあったとしても、当該情報αが管理単位Cで秘密管理されているのであれば、管理単位Cで当該情報αが生成・出力されたことの一事をもって、管理単位Cにおける秘密管理性が否定されることはないと考えられる。また、管理単位Dで当該生成AIから当該情報αがAI生成物として生成・出力されることがあったとしても、当該情報αが管理単位Cで秘密管理されているのであれば、管理単位Dで当該情報αが生成・出力されたことの一事をもって、管理単位Cにおける秘密管理性が否定されることはないと考えられる。
「有用性の考え方」についての改訂内容
営業秘密の要件のうち、有用性については実務上問題になることが少ないですが、改訂指針では、有用性が充足される場合を以下のとおり確認しています。
当該情報が、営業秘密を保有する事業者の事業活動に使用・利用されているのであれば、基本的に営業秘密としての保護の必要性を肯定でき、当該情報が公序良俗に反するなど保護の相当性を欠くような場合でない限り有用性の要件は充足されるものと考えられる。
また、有用性の要件の判断に際しては、当該情報を不正に取得した者がそれを有効に活用できるかどうかにより左右されないことも追記されています。
上記2点はいずれも昨今の裁判例における判断を踏まえた追記であり、有用性についての法解釈を確認するものといえます。
「非公知性の考え方」についての改訂内容
非公知性の考え方の項目では、昨今の裁判例や技術動向を踏まえた加筆が行われています。
まず、第三者からのハッキング等により営業秘密が、ダークウェブに公表されたとしても、その一事をもって直ちに非公知性を喪失するわけではないことが追記されました。
次に、公知情報の組み合わせについては、以下のように述べ、公知情報の組み合わせで非公知と言い得る例が追記されています。
例えば、公知情報の組み合わせであっても、その組み合わせが知られていなかったり容易に知り得ないため、財産的価値が失われていない場合には非公知と言いうる。また、仮に公知情報の組み合わせであって、その組み合わせが知られていたり容易であったりしたとしても、取得に要する時間や資金的コストがかかるため財産的価値があるという場合には非公知と言いうる。
また、非公知の情報といえるための要件として、進歩性(特許法29条2項)を有していることまでは要求しないとしています。これは、昨今の裁判例を踏まえた追記です。
さらに、リバースエンジニアリングによって営業秘密を抽出できる場合の非公知性の考え方についても項目が新設されました。改訂指針では、以下のとおり、抽出可能性の難度によって判断が分かれるとしています。
リバースエンジニアリングによって営業秘密を抽出できる場合、抽出可能性の難易度の差によって判断がわかれることになる。具体的には、誰でもごく簡単に製品を解析することによって営業秘密を取得できるような場合には、当該製品を市販したことによって営業秘密自体を公開したに等しいと考えられることから、非公知性を喪失すると考えられる。これに対し、特殊な技術をもって相当な期間が必要であり、誰でも容易に当該営業秘密を知ることができない場合には、当該製品を市販したことをもって非公知性を喪失するとはならない。
コメント
今回の営業秘密指針の改訂は、従来の法解釈に変更を加えるものではないものの、不正競争防止法において営業秘密と認められるための要件につき、雇用環境等の変化や昨今の裁判例を踏まえた考え方を整理しておく上で実務上参考となる内容です。
特に、秘密管理性の判断に際して、秘密情報の性質に応じて規範的な管理措置でも足りることを確認した点は重要といえるでしょう。
雇用の流動化や情報のデジタル化に伴い、営業秘密の盗用が報道されることも増え、企業の秘密管理は重要性を増しています。
営業秘密は企業の競争力の源泉となるものですので、これを機に改めて情報管理の在り方を点検することも考えられると思われます。
本記事に関するお問い合わせはこちらから。
(文責・町野)