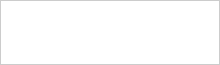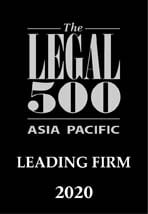東京地方裁判所民事第46部(高橋彩裁判長)は、本年(令和7年・2025年)1月14日、日本の登録商標や日本でサービスを提供する会社の商品等表示の外国企業による使用の差止請求や損害賠償請求について、日本の裁判所に国際裁判管轄がないとして請求を却下する判決をしました。
東京地方裁判所民事第46部(高橋彩裁判長)は、本年(令和7年・2025年)1月14日、日本の登録商標や日本でサービスを提供する会社の商品等表示の外国企業による使用の差止請求や損害賠償請求について、日本の裁判所に国際裁判管轄がないとして請求を却下する判決をしました。
なお、判決は、ドメイン名の不正取得行為については国際裁判管轄を認めつつ、本案で図利加害目的を否定し、請求を棄却していますが、ここでは、本案の判断の詳細には立ち入らず、主に国際裁判管轄の問題を取り上げます。
ポイント
骨子
- 被告が、本件ドメインを使用する権利の取得に当たって登録した住所は、「長崎県100 Hamilton Avenue, Suite 160, Palо Alto」であると認められる・・・ところ、これにより、被告の事務所又は営業所が日本国内にあるということにはならない。そして、被告が本件ドメインを使用する権利について上記のような住所を登録したからといって、被告が、日本の裁判所が民訴法3条の3第4号に基づく管轄権を有しない旨の抗弁を提出することが訴訟上の信義則に反するということはできない。
- 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき、民訴法3条の3第8号の規定に依拠して我が国の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、被告が日本国内でした行為により原告の権利利益について損害が生じたか、被告がした行為により原告の権利利益について日本国内で損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である(最高裁平成12年(オ)第929号、同年(受)第780号同13年6月8日第16二小法廷判決・民集55巻4号727頁及び最高裁平成23年(受)第1781号同26年4月24日第一小法廷判決・民集68巻4号329頁参照)。
- 民訴法3条の3第8号の「不法行為に関する訴え」は、違法行為により権利利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えをも含むものと解される。そして、このような差止請求に関する訴えについては、違法行為により権利利益を侵害されるおそれがあるにすぎない者も提起することができる以上は、同号の「不法行為があった地」は、違法行為が行われるおそれのある地や、権利利益を侵害されるおそれのある地をも含むものと解するのが相当である。
違法行為により権利利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えの場合において、同号の「不法行為があった地」が日本国内にあるというためには、被告が原告の権利利益を侵害する行為を日本国内で行うおそれがあるか、原告の権利利益が日本国内で侵害されるおそれがあるとの客観的事実関係が証明されれば足りるというべきである(前記最高裁平成26年4月24日判決参照)。 - 被告が、本件被告ウェブサイトにおける「AIに基づく契約書及び電子メールアカウントのレビュー」について、日本国内の利用者にサービスを提供していることを示す証拠は見当たらないところ、証拠(略)によれば、①本件被告ウェブサイトは全て英語で記載されていること、②本件被告ウェブサイトに掲載された価格表には、米国ドルでの価格が表示されており、円での価格は表示されていないこと、③本件被告ウェブサイトには、被告に対する問合せ先として、メールアドレス(略)とともに米国の住所及び電話番号が記載されており、日本の住所又は電話番号は記載されていないこと、④本件被告ウェブサイトには、日本語で作成された契約書又は日本法を準拠法とする契約書に関するレビューサービスについての記載はないこと、⑤本件被告ウェブサイトのサーバは米国に所在すること、⑥被告は、「LegalForce」の文字を含む標章を付した役務の提供を日本において申し出る計画を有していないことが認められる。以上の点を考慮すれば、本件被告ウェブサイトを日本において閲覧することができたことを踏まえても、本件被告ウェブサイトにおける被告標章(被告表示)の表示が、日本の需要者を対象としたものであるということはできず、これによって、原告の権利利益が日本国内で侵害され、又は侵害されるおそれがあり、また、原告の権利利益について日本国内で損害が生じたということはできない。
- 被告はインターネットブラウザ上に本件ドメインを入力すると、legalforcelawウェブサイトに自動的に接続されるように設定していることや、前記・・・のとおり、本件ドメインは日本を表す国別ドメイン名である「.jp」を含むこと並びに日本国内に所在するドメイン名登録機関が本件ドメインの登録及び管理をしていることに照らせば、被告が本件ドメインを使用することによって原告の特定商品等表示に係る権利利益が日本国内で侵害されるおそれがあるということができる。
- 訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解される(最高裁昭和60年(オ)第122号同63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁、最高裁平成7年(オ)第160号同11年4月22日第一小法廷判決・裁判集民事193号85頁及び最高裁平成21年(受)第1539号同22年7月9日第二小法廷判決・裁判集民事234号207頁参照)。
- (商標権及び不正競争防止法の商品等表示規制に基づく差止・損害賠償請求)に係る訴えは、被告の契約書レビューサービスの業務に関する訴えであるところ、本件被告ウェブサイトが日本の需要者を対象としたものであると認めることができないのは前記(略)のとおりであり、本件各証拠によっても、被告が日本において契約書レビューサービスの事業を行っていると認めることはできないから、上記訴えが被告の日本における業務に関するものであるということはできない。
- 本件請求6の3(本件ドメインに係る不正競争に基づく損害賠償請求)は、本件請求5(本件ドメインを使用する権利の保有及び本件ドメインの使用の差止請求)と訴訟物を異にするものの、本件請求5と同様に、本件ドメインを使用する権利の保有又は本件ドメインの使用が不競法2条1項19号の不正競争に該当することを理由とする請求であり、本件請求5と実質的に争点を同じくするものであることから、本件請求5との間に密接な関連があるということができる。
判決概要
| 裁判所 | 東京地方裁判所民事第46部 |
|---|---|
| 判決言渡日 | 令和7年1月14日 |
| 事件番号 事件名 |
令和5年(ワ)第70022号 商標権侵害行為等差止請求事件 |
| 裁判官 | 裁判長裁判官 髙 橋 彩 裁判官 杉 田 時 基 裁判官 吉 川 慶 |
解説
国際裁判管轄とは
国際裁判管轄とは、渉外的要素のある民事裁判事件についての裁判管轄をいいます。国際裁判管轄は、「国際」という言葉はつくものの、2つの国にまたがる紛争について、「どちらの国の裁判所が管轄を有するか」ということを考えるのではなく、実際に訴訟が提起された国において、「その国の裁判所は管轄を有するか」ということを考えるもので、性質的に国内法の問題です。
渉外事件における日本の裁判所の管轄権について、かつては、条理に基づいて判断されるべきものとされていましたが(最二判昭和56年10月16日昭和55年(オ)第130号民集第35巻7号1224頁「マレーシア航空事件」)、平成23年の民事訴訟法改正により、同法第1編第2章第1節に、「日本の裁判所の管轄権」に関する規定が定められました。
国際裁判管轄に関する民事訴訟法の規定は、同法3条の2から12まで多数ありますが、その中でも、原則に位置付けられる同法3条の2は、以下のとおり、1項において被告となる人の住所または居所が日本国内にある場合の管轄権を、また、3項において法人等の主たる事業所や営業所またはそれらが知れない場合に代表者等主たる業務担当者の住所が日本国内にある場合の管轄権を、それぞれ定めています。
(被告の住所等による管轄権)
第三条の二 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
(略)
3 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
知的財産権に関する民事訴訟の国際裁判管轄
登録にかかる知的財産権の存否・効力にかかる訴訟の国際裁判管轄
民事訴訟法3条の5第3項は、以下のとおり、知的財産権のうち、特許権等、設定の登録により発生するものの存否または効力に関する訴えにつき、登録地が日本の場合に日本の裁判所に管轄権が専属することを定めています。典型的には、特許審判の審決に対する取消訴訟等がこれにあたります。
(管轄権の専属)
第三条の五 (略)
3 知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。
国際専属管轄が法定されている場合、他の管轄原因で外国の裁判所に管轄が生じる場合でも、それを排斥することになるため、この規定は、「日本の裁判所が管轄を有するか」ということだけを定める通常の国際裁判管轄の考え方を超えた効果を持ちます。具体的には、日本で登録された権利が他国の裁判所で行使され、請求が認容されたとしても、日本国内での執行は認められませんし、外国訴訟と国内訴訟が競合した場合も、両者の調整はされず、我が国の訴訟を優先することになります。また、この規定の半面の効果として、外国で登録された権利の存否や効力について、我が国の裁判所は管轄権を有しないことになります。
侵害訴訟の国際裁判管轄
知的財産権侵害を理由とする請求には、差止請求と損害賠償請求とがありますが、これらのうち、まず、損害賠償請求についてみると、その根拠となる法律関係は、不法行為です。不法行為に基づく損害賠償請求の訴えについて、民事訴訟法3条の3第8号は、以下のとおり、「不法行為があった地」(不法行為地)が日本国内であるときに、日本の裁判所の管轄権を認めています。
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
(略)
八 不法行為に関する訴え 不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
(略)
不法行為地の意味として、最二判平成13年6月8日平成12年(オ)第929号民集55巻4号727頁「円谷プロダクション」事件は、以下のとおり述べ、加害行為が行われた場所(加害行為地)のほか、その結果が発生した場所(結果発生地)が含まれると解しています。
我が国に住所等を有しない被告に対し提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき,民訴法の不法行為地の裁判籍の規定(民訴法5条9号,本件については旧民訴法15条)に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには,原則として,被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である。けだし,この事実関係が存在するなら,通常,被告を本案につき応訴させることに合理的な理由があり,国際社会における裁判機能の分配の観点からみても,我が国の裁判権の行使を正当とするに十分な法的関連があるということができるからである。
これを前提に、上述の民事訴訟法3条の3第8号は、括弧書きの部分において、外国が加害行為地で日本が結果発生地である場合において、日本国内での結果発生が通常予見できないときは、日本の裁判所に管轄権がないことを定めています。
また、平成23年民事訴訟法改正後の最一判平成26年4月24日平成23年(受)第1781号民集第68巻4号329頁「眉トリートメント」事件は、同法3条の3第8号の解釈として、以下のとおり、「不法行為に関する訴え」は民法上の不法行為に基づく訴えに限られず、権利侵害の差止請求の訴えも含まれ、この場合の不法行為地には、加害行為のおそれのある地と結果発生のおそれのある地の双方が含まれると判示しています。
民訴法3条の3第8号の「不法行為に関する訴え」は,民訴法5条9号の「不法行為に関する訴え」と同じく,民法所定の不法行為に基づく訴えに限られるものではなく,違法行為により権利利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えをも含むものと解される(最高裁平成15年(許)第44号同16年4月8日第一小法廷決定・民集58巻4号825頁参照)。そして,このような差止請求に関する訴えについては,違法行為により権利利益を侵害されるおそれがあるにすぎない者も提起することができる以上は,民訴法3条の3第8号の「不法行為があった地」は,違法行為が行われるおそれのある地や,権利利益を侵害されるおそれのある地をも含むものと解するのが相当である。
この判決の考え方によると、侵害訴訟における差止請求と損害賠償請求の国際裁判管轄は、いずれも民事訴訟法3条の3第8号に基づいて決定されるものと考えられます。
なお、上記判決文中で引用されている最一決平成16年4月8日平成15年(許)第44号は、不正競争防止法違反に基づく差止請求権の不存在確認請求訴訟の国内管轄について判断を示したもので、不正競争防止法3条1項に基づく差止請求の訴えや差止請求権の不存在確認を求める訴えは、民事訴訟法5条9号の「不法行為に関する訴え」に該当するとしたものです。
知的財産権に関する民事訴訟におけるその他の管轄原因
以上のとおり、知的財産権に関する民事訴訟については、被告の住所等が国内にある場合に我が国の裁判所に管轄が認められるほか、登録にかかる権利の存否・効力については法定専属管轄が、差止請求・損害賠償請求については不法行為地を根拠とする管轄が、それぞれ適用されますが、それ以外にも、我が国の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合があります。
第1に、以下の民事訴訟法3条の8は、我が国の裁判所に管轄権がないとされる請求についても、被告が応訴した場合には管轄権が認められることを定めています(応訴管轄)。
(応訴による管轄権)
第三条の八 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
第2に、以下の同法3条の6は、ある請求に日本の裁判所の管轄権がない場合であっても、その請求と「密接な関連」のある他の請求について日本の裁判所に管轄権がある場合に、日本の裁判所の管轄権を認めています(併合管轄)。
(併合請求における管轄権)
第三条の六 一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
知的財産法分野で併合管轄が認められた代表的裁判例としては、著作権に関する上記「円谷プロダクション」事件判決があります。
第3に、以下の同法3条の7は、当事者が書面により、一定の法律関係に基づく訴えについての管轄裁判所の合意をしたときは、その裁判所に管轄権を認めています(合意管轄)。
(管轄権に関する合意)
第三条の七 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
4 外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
(略)
第4に、以下の同法3条の3第3~5号により、被告が国内に責任財産を有する場合や日本国内での業務に関する訴訟の場合等において一定の条件が充足される場合には、やはり我が国の裁判所に管轄権が認められます。
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
(略)
三 財産権上の訴え 請求の目的が日本国内にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。
四 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
五 日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え 当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。
(略)
なお、登録に基づく権利の存否・効力について国際法定専属管轄を規定した上記民事訴訟法3条の5はこれらの規定に優先しますので、日本の裁判所は、外国で登録された権利の存否・効力に関する訴えについては、上記各規定が管轄原因となることはありません。
特別の事情による訴えの却下
これまで述べてきた各規定によって我が国の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合であっても、民事訴訟法3条の9は、以下のとおり、「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるとき」は、訴えの全部または一部を却下できるとしています。
(特別の事情による訴えの却下)
第三条の九 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
間接管轄
国際裁判管轄を考えるにあたり、常に意識しておく必要があるのは、間接管轄の問題です。
裁判は国家の主権の行使ですから、判決の効力が及ぶのは、原則として、当該国の主権が及ぶ領域内に限られ、外国で判決を執行するためには、その国で判決の承認を受け、執行判決を得る必要があります。そもそも外国判決を承認しない国もありますが、我が国は、一定の要件のもとこれを認めています。
日本の法令の中で、執行判決について規定するのは民事執行法24条で、同条5項は、執行判決を求める訴えの要件として、以下のとおり、民事訴訟法118条各号の要件を充足することを求めています。
(外国裁判所の判決の執行判決)
第二十四条 (略)
5 第一項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第百十八条各号(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。
(略)
民事訴訟法118条は、外国裁判所の確定判決の効力が承認されるための要件を定めた規定で、以下のとおり、その1号において、「法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること」を求めています。
(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。
分かりにくいのですが、ここにいう「法令」は日本の法令ですので、外国の裁判所が自国に管轄権があると判断して判決をしたとしても、日本の裁判所は、別途日本の法令や条約に則ってその外国裁判所に管轄権があったかどうかを判断することになります。そして、もし、日本の裁判所が、判決国の裁判所には管轄権がなかったと判断すると、上記要件を充足しないことになり、その判決は、承認を受けることができなくなります。
具体的な事案として、上述の「眉トリートメント事件」判決では、米国の原告が日本法人に営業秘密の利用を許諾したところ、当該日本法人の元社員が日本で当該営業秘密を利用したため、米国カリフォルニア州で当該元社員に対する訴えを提起し、損害賠償と差止を命じる確定判決を得たという事案で、日本でその執行を求める訴えを提起しましたが、最高裁判所は、米国で損害が発生していないことから、日本法の下では米国裁判所に管轄権がないとして、原告の請求を棄却しました。また、下級審においては、日本の特許権の移転登録請求を認容した外国判決について、民事訴訟法3条の5第3項による専属管轄に反するものとして承認執行を否定した判決もあります(名古屋高判平成25年5月17日平成24年(ネ)第1289号)。
なお、紛争解決手段として当事者が仲裁を選択した場合には、承認執行の可否は、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)5条によって決定されることになるところ、同条は間接管轄の問題をもって承認執行を否定する理由とはしていないため、判決執行における上述のような問題は生じません。これが、しばしば国際契約における紛争解決手段として仲裁が選択される大きな理由ですが、知的財産権に関する民事訴訟の多くは、知的財産権の侵害など、契約に基づかない法律関係を巡るものであるため、仲裁合意が存在するのは例外的な場合にとどまります。
事案の概要
本件の原告と被告とは、いずれも契約書レビュー等の法務関連のサービスをオンラインで提供する会社で、原告は日本法人、被告は米国カリフォルニア州の法人ですが、いずれも「LegalForce」を含む商標を用い、また、社名にも「LegalForce」の文字が含まれていました(原告は、訴え提起後に社名を変更しています。)。
被告は、原告に対し、2022年6月24日、米国連邦地方裁判所で商標権侵害を理由とする訴訟を提起し、原告は、被告に対し、2023年1月20日、東京地方裁判所で、商標権侵害等を理由として、本訴訟を提起しました。
原告の被告に対する請求は、以下のようなものです。
| 本件請求1 | 商標権侵害を理由とする被告の契約書レビューサービスの提供に関する広告・価格表における被告標章の差止請求 |
|---|---|
| 本件請求2 | 同理由に基づく被告標章を付したウェブサイトの削除請求 |
| 本件請求3 | 不正競争防止法2条1項1、2号違反を理由とする契約書レビューサービスの提供に関する広告・価格表における被告表示の差止請求 |
| 本件請求4 | 同理由に基づくウェブサイト等からの被告表示の削除請求 |
| 本件請求5 | 不正競争防止法2条1項19号違反を理由とする「legalforce.jp」のドメイン名の使用等差止請求 |
| 本件請求6の1 | 商標権侵害を理由とする損害賠償請求 |
| 本件請求6の2 | 不正競争防止法2条1項1、2号違反を理由とする原告表示に係る損害賠償請求 |
| 本件請求6の3 | 不正競争防止法2条1項19号違反を理由とする本件ドメインに係る損害賠償請求 |
| 本件請求7 | 米国における不当訴訟を理由とする損害賠償請求 |
以上の請求について、原告は、以下の各規定に基づき、上記の本件各請求につき、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められると主張しました。
- 民事訴訟法3条の3第4号に基づく国際裁判管轄(日本国内に事業所等がある場合における当該事業所等における業務に関する訴え)
- 民事訴訟法3条の3第5号に基づく国際裁判管轄(日本における業務に関する訴え)
- 民事訴訟法3条の3第8号に基づく国際裁判管轄(不法行為地)
- 民事訴訟法3条の6に基づく国際裁判管轄(併合管轄)
判旨
民事訴訟法3条の3第4号に基づく国際裁判管轄について
民事訴訟法3条の3第4号は、上述のとおり、「事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの」について「当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき」に我が国の裁判所の管轄権を認めており、原告は、これを国際裁判管轄の根拠として主張していました。
しかし、被告は、日本に事業所や営業所を有しない米国法人ですので、判決は、以下のとおり述べ、この主張を排斥しました。
・・・被告は、米国において設立された法人で、米国カリフォルニア州に主たる事務所を有しており、本件各証拠によっても、被告の事務所又は営業所が日本国内にあると認めることはできない。
原告は、上記主張にあたり、被告が日本で「.jp」ドメインのドメイン名を取得していたところ、「.jp」ドメインのドメイン名を取得するためには、日本に住所があることが求められます。この点、被告は、同ドメイン名の取得に際し、「長崎県100 Hamilton Avenue, Suite 160, Palo Alto」という住所を登録していたことから、原告は、被告による管轄権にかかる抗弁の主張は訴訟上の信義則に反すると主張していました。
しかし、判決は、以下のとおり、そのような住所登録をしたからといって日本に住所地があるとはいえず、また、管轄権に関する抗弁の提出が訴訟上の信義則に反することにもならないとして、同主張を排斥しています。
被告が、本件ドメインを使用する権利の取得に当たって登録した住所は、「長崎県100 Hamilton Avenue, Suite 160, Palо Alto」であると認められる・・・ところ、これにより、被告の事務所又は営業所が日本国内にあるということにはならない。そして、被告が本件ドメインを使用する権利について上記のような住所を登録したからといって、被告が、日本の裁判所が民訴法3条の3第4号に基づく管轄権を有しない旨の抗弁を提出することが訴訟上の信義則に反するということはできない。
民事訴訟法3条の3第8号に基づく国際裁判管轄について
民事訴訟法3条の3第8号は、上述のとおり、日本国内が不法行為地である場合に我が国の裁判管轄権を承認する規定です。その適否に関し、判決は、まず、以下のとおり、円谷プロダクション事件判決や眉トリートメント事件判決を引用し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について国際裁判管轄を認めるためには、加害行為地または結果発生地が日本国内であることの証明があればよいとの考え方を示しました。
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき、民訴法3条の3第8号の規定に依拠して我が国の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、被告が日本国内でした行為により原告の権利利益について損害が生じたか、被告がした行為により原告の権利利益について日本国内で損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である(最高裁平成12年(オ)第929号、同年(受)第780号同13年6月8日第16二小法廷判決・民集55巻4号727頁及び最高裁平成23年(受)第1781号同26年4月24日第一小法廷判決・民集68巻4号329頁参照)。
また、判決は、続けて、以下のとおり、眉トリートメント事件判決に基づき、「不法行為に関する訴え」には権利侵害行為に対する差止請求も含まれ、不法行為地については、権利侵害のおそれまたは結果発生のおそれが証明されれば足りるとの考え方を示しました。
民訴法3条の3第8号の「不法行為に関する訴え」は、違法行為により権利利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えをも含むものと解される。そして、このような差止請求に関する訴えについては、違法行為により権利利益を侵害されるおそれがあるにすぎない者も提起することができる以上は、同号の「不法行為があった地」は、違法行為が行われるおそれのある地や、権利利益を侵害されるおそれのある地をも含むものと解するのが相当である。
違法行為により権利利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えの場合において、同号の「不法行為があった地」が日本国内にあるというためには、被告が原告の権利利益を侵害する行為を日本国内で行うおそれがあるか、原告の権利利益が日本国内で侵害されるおそれがあるとの客観的事実関係が証明されれば足りるというべきである(前記最高裁平成26年4月24日判決参照)。
その上で、判決は、まず、本件請求1から4まで、6の1及び6の2(商標法及び商品等表示に関する不正競争防止法に基づく請求)にかかる訴えについて、被告ウェブサイトにおける「LegalForce」の表示は日本の需要者に向けられたものではなく、日本国内での権利利益の侵害や損害はないとして、管轄権を否定しました。
被告が、本件被告ウェブサイトにおける「AIに基づく契約書及び電子メールアカウントのレビュー」について、日本国内の利用者にサービスを提供していることを示す証拠は見当たらないところ、証拠(略)によれば、①本件被告ウェブサイトは全て英語で記載されていること、②本件被告ウェブサイトに掲載された価格表には、米国ドルでの価格が表示されており、円での価格は表示されていないこと、③本件被告ウェブサイトには、被告に対する問合せ先として、メールアドレス(略)とともに米国の住所及び電話番号が記載されており、日本の住所又は電話番号は記載されていないこと、④本件被告ウェブサイトには、日本語で作成された契約書又は日本法を準拠法とする契約書に関するレビューサービスについての記載はないこと、⑤本件被告ウェブサイトのサーバは米国に所在すること、⑥被告は、「LegalForce」の文字を含む標章を付した役務の提供を日本において申し出る計画を有していないことが認められる。以上の点を考慮すれば、本件被告ウェブサイトを日本において閲覧することができたことを踏まえても、本件被告ウェブサイトにおける被告標章(被告表示)の表示が、日本の需要者を対象としたものであるということはできず、これによって、原告の権利利益が日本国内で侵害され、又は侵害されるおそれがあり、また、原告の権利利益について日本国内で損害が生じたということはできない。
他方、判決は、本件請求5(不正競争防止法上のドメイン名の不正取得行為を理由とする差止請求)にかかる訴えについて、「.jp」が日本を表す国別ドメイン名であり、ドメイン名登録機関が日本国内に所在することを前提に、被告が「legalforce.jp」を使用していることによって、原告の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するもの)にかかる権利利益が日本国内で侵害される恐れがあるとして、管轄権を肯定しました。
前記前提事実・・・のとおり、被告はインターネットブラウザ上に本件ドメインを入力すると、legalforcelawウェブサイトに自動的に接続されるように設定していることや、前記・・・のとおり、本件ドメインは日本を表す国別ドメイン名である「.jp」を含むこと並びに日本国内に所在するドメイン名登録機関が本件ドメインの登録及び管理をしていることに照らせば、被告が本件ドメインを使用することによって原告の特定商品等表示に係る権利利益が日本国内で侵害されるおそれがあるということができる。
本件請求7(米国における不当訴訟を理由とする損害賠償請求)にかかる訴えについて、判決は、まず、以下のとおり、不当訴訟の成立要件について判示した最三判昭和63年1月26日昭和60年(オ)第122号民集42巻1号1頁を引用し、訴え提起が不法行為となるのは、「当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる」との考え方を示しました。
訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解される(最高裁昭和60年(オ)第122号同63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁、最高裁平成7年(オ)第160号同11年4月22日第一小法廷判決・裁判集民事193号85頁及び最高裁平成21年(受)第1539号同22年7月9日第二小法廷判決・裁判集民事234号207頁参照)。
その上で、判決は、以下のとおり、被告が米国で訴えを提起したのは、原告が大規模な資金調達をして「LegalForce」の名称を用いて米国に進出する旨の発表をしたのがきっかけであり、訴訟の経過に照らしても、被告による米国訴訟が事実的法的根拠を欠くものであることが明らかであったとはいえない等と述べて、不当訴訟にはあたらないとし、管轄権を否定しました。
前記(略)によれば、被告は、「LegalForce」の文字を含む標章に係る被告米国商標権を有していたところ、商号を株式会社LegalForceとし、日本において「LegalForce」の名称を用いてサービスを提供していた原告が、大規模な資金調達をして、米国を中心として海外進出をする旨の発表をしたことを受け、原告に対し、被告米国商標権の侵害等を主張して、本件米国訴訟を提起したものであるということができる。これに加えて、前記・・・の本件米国訴訟の経緯に照らせば、被告による本件米国訴訟の訴状が二度にわたり訂正されるとともに、米国裁判所における審理及び管轄権に関する証拠開示手続を経た結果として、米国裁判所は本件米国訴訟の第二訂正訴状を却下する決定をしたものということができる。
これらの事情に照らせば、被告が本件米国訴訟を提起した時点において、本件米国訴訟において被告の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであることが明らかであったとはいえず、被告が、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したということはできない。そうすると、被告による本件米国訴訟の提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものということはできない。そして、これを前提として、前記・・・の本件米国訴訟の経緯を考慮すれば、被告による本件米国訴訟の訴訟追行が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものということもできない。
なお、知的財産権の行使について不当訴訟と認めた最近の判決として、漏水位置検知装置事件大阪地裁判決及び螺旋状コイルインサートの製造方法事件東京地裁判決を紹介していますので、ご覧ください。
民事訴訟法3条の3第5号に基づく国際裁判管轄について
民事訴訟法3条の3第5号は、上述のとおり、日本において事業を行う者に対し、訴えがその者の日本における業務に関するものであるときに我が国の裁判所の国際裁判管轄を承認する規定です。この規定の適用につき、判決は、以下のとおり、被告は日本の需要者に向けたサービスを提供していない以上、訴えが被告の日本における業務に関するものとはいえないとして、管轄を否定しました。
本件請求1から4まで、6の1及び6の2に係る訴えは、被告の契約書レビューサービスの業務に関する訴えであるところ、本件被告ウェブサイトが日本の需要者を対象としたものであると認めることができないのは前記(略)のとおりであり、本件各証拠によっても、被告が日本において契約書レビューサービスの事業を行っていると認めることはできないから、上記訴えが被告の日本における業務に関するものであるということはできない。
また、legalforcelawウェブサイトに、被告が商標登録出願について日本に顧客を有することをうかがわせる記載があり、被告が日本の顧客44名について商標登録出願をしたことが認められるのは、前記(略)のとおりであるが、本件請求1から4まで、6の1及び6の2に係る訴えは、契約書レビューサービスに関するものであって、被告の商標登録出願に関するものではないから、被告の商標登録出願についての事情は、上記判断を左右するものではない。
民訴法3条の6に基づく国際裁判管轄について
民訴法3条の6は、上述のとおり、我が国の裁判所が管轄を有する訴えと請求に密接な関連のある訴えについて併合管轄を認める規定です。
この規定の適用につき、判決は、本件請求6の3(不正競争防止法上のドメイン名の不正取得行為を理由とする損害賠償請求)について、本件請求5(同理由に基づく差止請求)と密接な関連があるとして、管轄権を肯定しました。
本件請求6の3は、本件請求5と訴訟物を異にするものの、本件請求5と同様に、本件ドメインを使用する権利の保有又は本件ドメインの使用が不競法2条1項19号の不正競争に該当することを理由とする請求であり、本件請求5と実質的に争点を同じくするものであることから、本件請求5との間に密接な関連があるということができる。
他方、その余の請求については、ドメインを巡る問題とは関係ないとして、併合管轄を否定しました。
これに対し、本件各請求のうち本件請求5及び6の3を除く部分は、前記第2の1のとおり、いずれも本件請求5と訴訟物を異にする上、本件請求1、2及び6の1は、本件被告ウェブサイトにおいて、契約書レビューサービスの提供に関する広告及び価格表について被告標章を付して電磁的方法により提供することによって、原告各商標権が侵害されたこと、本件請求3、4及び6の2は、契約書レビューサービスの提供に被告表示を使用することが、不競法2条1項1号及び2号の不正競争に該当すること、本件請求7は、本件米国訴訟の提起及び訴訟追行が不法行為に当たることを理由とする請求であって、本件ドメインを使用する権利の保有又は本件ドメインの使用が同項19号の不正競争に該当することを理由とする本件請求5と実質的に争点を同じくするということはできないから、本件請求5との間に密接な関連があるということはできない。
結論
以上のとおり、判決は、本件請求5にかかる訴えについては、不法行為地を日本と認め、民事訴訟法3条の3第8号に基づく国際裁判管轄を肯定し、また、本件請求6の3にかかる訴えについては、本件請求5にかかる訴えに密接に関連するものとして、同法3条の6に基づく併合管轄を肯定しましたが、その余の訴えについては、我が国の裁判所に国際裁判管轄がないとして、訴えを却下しました。
なお、国際裁判管轄が認められた本件請求5および6の3にかかる訴えについては、本案の審理の対象とされましたが、被告は、原告による「LegalForce」の商号や原告各商標の使用開始前から、本件ドメインを使用する権利を保有し、現に米国で使用していたことや、本件ドメインが入力された場合に自動的に接続されるlegalforcelawウェブサイトは、被告の米国での法律業務に関連するものであることから、被告には図利加害目的が認められないとして、請求を棄却しています。
コメント
本判決は、商標権侵害や不正競争防止法違反、不当訴訟を理由とする請求について国際裁判管轄にかかる判断を示したものとして参考になるため、紹介しました。
追記(2026年2月7日)
内容に一部誤りがあったため、修正しました。
本記事に関するお問い合わせはこちらから。
(文責・飯島)