 報道によると、本年(平成29年)3月2日、フランク三浦事件についての最高裁判決があり、フランク三浦側が勝訴したとのことです。おそらく、上告及び上告受理申立てが排斥されたものと考えられます。
報道によると、本年(平成29年)3月2日、フランク三浦事件についての最高裁判決があり、フランク三浦側が勝訴したとのことです。おそらく、上告及び上告受理申立てが排斥されたものと考えられます。
本訴訟は、「フランク三浦」の商標を登録することが適法か、ということが争われた行政訴訟です。フランク三浦側が勝訴したということは、商標登録が維持されたということで、くだんの時計を製造販売することが適法かどうかは判断されていません。
とはいえ、特許の場合と異なり、商標登録が維持されると、商標権侵害が認められる可能性は低くなります。特許の場合は、過去の発明を内包していても、進歩性があれば特許性が認められますが、商標の場合、他の商標と類似する商標は登録が認められず、逆に登録が認められた場合には、類似性がないと認定されたことになるからです。
登録要件における類似の判断と商標権侵害における類似の判断とは必ずしも同一とは限らず、また、不正競争防止法の問題は残りますが、それでもフランク三浦側にとっては大きな勝利といえるでしょう。
手続的には、最高裁判所で知財高裁判決が維持されたことにより、知財高裁による原審決の取消が確定するため、特許庁における商標登録無効審判が再開され、改めて、審判請求不成立(フランク三浦の商標登録を維持)の審決がなされることになると考えられます。
さて、フランク三浦判決については、すでに知財高裁の判断について紹介記事を書きましたが、今回は、パロディ商標をめぐる過去の訴訟を概観し、改めてフランク三浦判決の位置付けについて検討したいと思います。
フランク三浦事件
事件の経緯
フランク三浦訴訟は、下記の表の「引用商標」の3件の商標登録を受けているフランクミュラー側が、「本件商標」についてフランク三浦が受けている商標登録は無効であるとして特許庁に商標登録無効審判を請求したことに始まります。
| 本件商標 | 引用商標 |
|---|---|
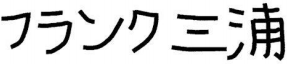 |
「フランク ミュラー」(標準文字)
|
特許庁は、平成27年9月8日、フランクミュラー側の請求を認め、周知商標類似(商標法4条1項10号)、先願商標類似(同項11号)、出所混同の怖れ(同項15号)、著名商標の不正目的使用(19号)の4つの理由を挙げて、フランク三浦の商標登録は無効であるとの審決をしました(無効2015-890035号)。
この審決を不服としてフランク三浦側が知財高裁に出訴し、結論として特許庁の審決が覆されたのが、昨年話題になったフランク三浦事件知財高裁判決です。
適用が問題となった商標法の具体的規定は以下のようなものです。
| 商標法4条1項10号 | 他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの |
|---|---|
| 商標法4条1項11号 | 他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの |
| 商標法4条1項15号 | 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標 |
| 商標法4条1項19号 | 他人の著名商標と同一又は類似の商標で不正の目的をもって使用する商標 |
知財高裁の判断
知財高裁は、本件商標と引用商標とは、称呼において類似するものの、外観や観念は異なるとして、両者の類似性を否定し、商標法4条1項10号、11号及び19号該当性を否定しました。
また、通常の注意力をもってすれば、誤認混同の恐れもないとして、15号の該当性も否定しました。
商標の類似性判断
氷山印事件
商標の類否判断の考え方を示したリーディングケースといえるのは、以下の判示をした最三判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁(氷山印事件)です。
商標の類似は,対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり,その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする
ここでポイントとなっているのは、以下の3点です。
- 商標の類否判断は、「取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察」すべきであること
- 「取引者に与える印象、記憶、連想等」は、「外観、観念、称呼」によるものであること
- 判断は、「具体的な取引状況」に基づいてなされること
保土ヶ谷化学工業社標事件
氷山印事件判決では、商標の類否判断に際し、「具体的な取引状況」を考慮すべきであることが示されましたが、どの程度具体的な状況を考慮するのかについては、最一判昭和49年4月25日審決取消訴訟判決集昭和49年443頁(保土ヶ谷化学工業社標事件)が、以下の判示をしています。
商標の類否判断において考慮することの出来る取引の実情とは,その指定商品全体についての一般的・恒常的なそれを指すものであって,単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的,限定的なそれを指すものではないことは明らかであ(る)
つまり、腕時計の商標が問題となる場合には、腕時計一般の取引状況が考慮対象となるのであって、フランクミュラーの取引状況やフランク三浦の取引状況を考慮するわけではない、というのがこの判例からの帰結といえます。
パロディ商標をめぐる裁判例
「パロディは、現代の慣用においては他の芸術作品を揶揄や風刺、批判する目的を持って模倣した作品、あるいはその手法のことを指す」(Wikipediaより)とされています。
つまり、パロディは本質的に模倣であり、知的財産法による規制の対象となりやすい性質を有しているといえます。
他方で、パロディが揶揄や風刺、批判のための表現であるためには、オリジナルと識別可能であることが条件といえます。つまり、見る者に揶揄や風刺、批判といった意図を伝達できるだけのオリジナリティがあることが、パロディの成立要件ともいえるのです。
これは、知的財産権の侵害を否定する方向に働く事情です。
このようなパロディの二面性は、特にオリジナリティが直接的に議論の対象となる著作権法の領域で顕在化し、わが国でもいくつか著名な裁判例があります。
比較法的に見ると、フランス著作権法は、明文でパロディを非侵害とし、また、米国では、フェアユース規定によって一定範囲の免責が認められています。
類似とされた例
著作権法と異なり、商標法では、フランク三浦事件に見られるように、類似性や誤認混同の恐れなどが争点となります。
過去に類似とされたパロディ商標の例としては、以下のようなものがあります。
BOZU事件(特許庁平成10年異議第90851号)


ランボルミーニ事件(知財高判平成24年5月31日)


KUMA事件(知財高判平成25年6月27日)


非類似とされた例
他方、いわゆるパロディ商標であっても、非類似とされた例はあります。
比較的最近の代表的事例としては、以下のSHI-SA事件があげられるでしょう。
SHI-SA事件(知財高判平成22年7月12日)


KUMA事件とSHI-SA事件
上記の事件の中でも、KUMA事件とSHI-SA事件は、いずれもPUMAの商標との類似が問題となり、結論が類似と非類似に分かれたことから、対比の素材として興味深いものといえます。
両者を比較すると、KUMA事件の商標は、北海道の土産物ながら、これを付した商品が百貨店などでも広く販売されており、判決は、以下のように述べています。
取引者,需要者は,顕著に表された独特な欧文字4字と熊のシルエット風図形との組合せ部分に着目し,周知著名となっている引用商標を連想,想起して,当該商品が被告又は被告と経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれがある。
「PUMA」に対応する4文字の単語「KUMA」と、その横のシルエットの組合せが出所混同をもたらす可能性があるという考え方です。
他方のSHI-SA事件の商標は、沖縄県内のみかつごく小規模でしか使用されておらず、判決は、以下のように述べて、そのような取引状況を勘案することができるとしました。
取引の実情として,現実の使用態様を勘案することができる。
具体的な判断としては、以下のように述べています。
登録商標の指定商品・・・の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としても,該登録商標をその指定商品に使用したときに,当該商品がプーマ社又は同社と一定の緊密な営業上の関係若しくは同社と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるとはいえない。
確かに、「SHI-SA」については、文字の部分が「KUMA」のような4文字で構成されているわけではなく、パロディとしてみた場合の面白みには欠けるかもしれませんが、「PUMA」との違いは比較的明確であるといえるでしょう。
ただ、ここで注目すべきは、類似性を否定する根拠として、沖縄県内のみかつごく小規模でしか使用されていないという個別具体的な事情を考慮していることです。
一般論としては、取引状況を具体的に見れば見るほど、事業者間の取引状況の相違が顕著になるといえるでしょうから、類似性を否定する方向に作用するといえます。両事件では、文字部分において、文字数や内容などに違いがあるため、基本的には、この点が結論の違いに影響したものと思われますが、SHI-SA事件では、保土ヶ谷化学工業社標事件において想定されているよりも具体的な取引態様が、非類似判断の補強材料とされていることは間違いありません。
フランク三浦判決の位置付け
判決における具体的事情の考慮
さて、フランク三浦事件において、フランクミュラー側(被告)は、フランク三浦商標の具体的な利用形態について、以下のような主張をしていました。
原告が被告商品と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売していること,本件商標は引用商標を模倣したものであることに照らすと,原告商品と被告商品との間で関連付けが行われ,原告商品が被告と経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれがあることは否定できない
これに対し、判決は、以下のように述べ、パロディ製品が発売されたのはフランク三浦商標の登録後であって、そもそもフランク三浦商標が具体的にどのように利用されているかは考慮の対象とならないと判示しました。
そもそも,原告が本件商標を付した時計の販売を開始したのは,本件商標の商標設定登録以後であることは当事者間に争いがない上に,本件において提出された原告商品の形態を示す証拠は,いずれも,本件商標の登録査定時よりも後の原告商品の形態を示すものであることからすると,原告が被告商品と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売しているとの被告の主張は,本件商標の登録査定時以後の事情に基づくものであり,それ自体失当である。
判決は、さらに続けて、以下の通り、極めて具体的な取引状況を認定して、それを類似性否定の根拠としています。
仮に,この事情を考慮したとしても,本件商標と引用商標1とでは前記・・・のとおり,観念や外観において大きな相違があること,被告商品は,多くが100万円を超える高級腕時計であるのに対し・・・,原告商品は,その価格が4000円から6000円程度の低価格時計であって,原告代表者自身がインタビューにおいて,「ウチはとことんチープにいくのがコンセプトなので」と発言しているように,被告商品とはその指向性を全く異にするものであって,取引者や需要者が,双方の商品を混同するとは到底考えられないことなどに照らすと,上記事情は,両商標が類似するものとはいえないとの前記の認定を左右する事情とはいえない。
このような判断手法は、SHI-SA事件に見られる判断手法に近いといえるでしょう。
パロディ商標と商標権侵害訴訟
ここまで検討してきたのは、商標登録の可否ないし有効性の問題でした。
他方、パロディ商標は、商標権侵害訴訟でも問題となることがあります。有名なものとしては、判決には至っていないものの、「面白い恋人」事件があります。


取引の実情の考慮
商標権侵害訴訟では、侵害の認定に際し、商標的使用の認定を含め、より個別具体的な事情が考慮される傾向にあるとはいえるでしょう。
しかし、ある具体的状況で区別できれば商標権侵害ではない、という論理が一般化すると、世の中は模倣品だらけになってしまいます。
商標登録の段階で具体的な事情を考慮すると、影響はさらに大きくなります。ある時点での具体的事情をもとに商標登録が認められたとしても、その前提の事情は変化するかもしれないからです。
例えば、「ウチはとことんチープにいくのがコンセプト」という前提でフランク三浦の商標の登録を認めたとしても、いずれ高級路線に転換しないとは限らないのです。
最高裁判所が、保土ヶ谷化学工業社標事件において、考慮すべき取引の実情を指定商品全体の実情という、ある程度抽象化されたレベルにとどめたのは、このような事情があると思われます。
他方、フランク三浦の商標についてみれば、字体などからも、フランクミュラーとは全く異なるブランドであることが明らかで、わが国の知的財産制度がこういったユーモアを(フランク三浦の結論の是非はさておき)いかなる場合も許さない世の中を目指すことにしても良いのか、という素朴な疑問も感じます。
また、SHI-SA事件判決にしても、フランク三浦事件判決にしても、対比された両商標が非類似であるとの結論を導くために、具体的な商品についての取引状況を認定する必要があったのか、という点にも疑問は残ります。
特に、フランク三浦事件での具体的な取引状況の考慮は、やはり具体的な取引状況を主張した被告の主張への反駁として述べられたもので、結論を導く上で中心的な論拠となっているわけでもありません。
最高裁判所は、フランク三浦事件では沈黙しました。論理構成はともかく、結論は変わらなかったということかも知れませんし、現状の問題は従来最高裁判所が示してきた規範で対応することができるということでしょう。今後、限界事例が蓄積したときに、どのような判断が示されるのかを待ちたいと思います。
本記事に関するお問い合わせはこちらから。
(文責・飯島)












