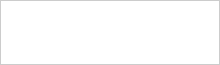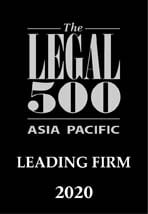東京地方裁判所民事第40部(中島基至裁判長)は、令和6年9月26日、新聞紙面に掲載された写真をスマートフォンで撮影しその画像を被告が自らの投稿文章と併せてツイッターに投稿した行為につき、原告が保有する新聞掲載写真の著作権の侵害が争点となった訴訟において、著作権法上の引用に該当し適法である旨の判断をしました。
東京地方裁判所民事第40部(中島基至裁判長)は、令和6年9月26日、新聞紙面に掲載された写真をスマートフォンで撮影しその画像を被告が自らの投稿文章と併せてツイッターに投稿した行為につき、原告が保有する新聞掲載写真の著作権の侵害が争点となった訴訟において、著作権法上の引用に該当し適法である旨の判断をしました。
本件判決は、引用の成否の判断について、他人の著作物を利用する目的、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の程度などを総合考慮して判断されるべきと述べたうえ、当てはめでは原告の経済的利益への影響についても言及しています。
本件は、著作権法上の引用の要件について参考になりますので、ご紹介します。
ポイント
骨子
- 著作権法32条1項は、公表された著作物は、公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で、引用して利用することができる旨規定するところ、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内であるかどうかは、社会通念に照らし、他人の著作物を利用する目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の程度などを総合考慮して判断されるべきである。
- 新聞の紙面に掲載された本件の各写真(以下「本件各写真」)の構図は総じてありふれたものであり、ツイッターに投稿された写真に映し出された本件各写真は、全体として不鮮明であり、その画質は粗く細部は捨象されていることが認められる。そうすると、仮に本件各写真に創作的表現部分があったとしても、ツイッターに投稿された上記写真に映し出された本件各写真は、そのごく僅かな部分を複製するものにすぎない。
- ツイッターに投稿された上記写真に映し出された本件各写真の上記態様に鑑みると、その不鮮明な本件各写真が独立して二次的に利用されるおそれは、極めて低いというべきであり、本件全証拠によっても、二次的に利用されたことによって原告が経済的利益を得る機会を現に失ったことを認めるに足りない。
- 本件各写真の性質、その利用目的、ツイッターへの掲載態様、著作権者である原告に及ぼす影響の程度などを、 社会通念に照らして総合考慮すれば、本件各写真をスマートフォンで写してこれをツイッターに掲載して利用する行為は、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内であると認めるのが相当である。
判決概要
| 裁判所 | 東京地方裁判所民事第40部 |
|---|---|
| 判決言渡日 | 令和6年9月26日 |
| 事件番号 | 令和5年(ワ)第70388号 |
| 裁判官 | 裁判長裁判官 中島 基至 裁判官 古賀 千尋 裁判官 坂本 達也 |
解説
著作権法上の引用とは
著作物を権利者の許諾なくして複製したり公衆送信したりする行為は、著作権侵害となります。ただし、著作権法はいくつもの権利制限規定を設けており、それら権利制限規定の定める行為類型に該当すれば、当該規定に基づき著作権侵害を免れることになります。
実務上よく使われる権利制限規定の1つに、著作物の引用があります(著作権法32条)。条文は以下のとおりです。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 (略)
主従関係性・明瞭区別性と総合考慮説
条文上、引用に該当するための要件には
①公表された著作物であること
②引用であること
③公正な慣行に合致すること
④報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれること
があります。
また、適法な引用の基準として、(i)明瞭区別性と(ii)主従関係性を要求する考え方が昭和55年のパロディモンタージュ事件最高裁判決[1]で示され、その後の下級審裁判例もこれにならい、明瞭区別性と主従関係性を中心的な要件として検討するものが見られました。
明瞭区別性とは、引用している部分と引用されている部分が明瞭に区別されていることです。主従関係性とは、引用している部分が主、引用されている部分が従という関係が存在することです。
ただし、パロディモンタージュ事件は旧著作権法下の事件ということもあり、これらの明瞭区別性と主従関係性が、現行の著作権法32条の要件として条文上どこから読み取れるのかは明確ではありません。最近では、その位置づけの再構成を試みる議論もなされており、学説上は、引用という言葉の意味から導かれる要件として考える見解が有力かと思われます[2]。
他方、明瞭区別性と主従関係性には正面から言及せずに判断をする下級審裁判例も見られるようになっています。
その代表的なものとして、知財高判平22年10月13日・平成22年(ネ)第10052号[絵画鑑定書事件]は、以下のとおり、利用の目的・方法・態様、利用される著作物の種類や性質、著作権者に及ぼす影響の有無・程度を総合考慮して判断すると述べています。
他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり,かつ,引用の目的との関係で正当な範囲内,すなわち,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり,著作権法の上記目的をも念頭に置くと,引用としての利用に当たるか否かの判断においては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。
その後の地裁・高裁レベルの判決にもこれにならうものがあります。このような立場を総合考慮説と呼ぶことがあります。
また、例えば別稿で紹介した令和4年11月2日の知財高裁判決など、上記③公正な慣行に合致すること及び④報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることを引用の要件として挙げたうえで、主従関係性や明瞭区分性には触れず、総合考慮説のような規範も特段提示せずに検討を加える下級審裁判例もあります。
さらに、知財高判令和5年4月17日・令和4年(ネ)第10104号は、総合考慮説に沿った規範を示しつつ、「「主従関係」の有無は、「引用」の成否を判断する考慮要素の一つにすぎず、それのみで「引用」の成否が決まるものではない」と言及しています。
このように、裁判所の判断基準はいまだ統一されていない状況ということができるでしょう。
引用する側が著作物であることの要否
適法な引用の要件として、引用して利用する側が著作物であることが適法な引用の要件として必要か否かについても、議論があります。
著作権法32条を新たな創作を保護するための制度と捉えるならば、著作物性を必要とする方向の解釈となりますが、旧著作権法にあった「自己ノ著作物中ニ」節録引用できるとの文言が削除された立法経緯などから、著作物性を不要とする見解も有力です。上記平成22年の知財高裁判決は、著作物であることを必要としない立場を示しています。
事案の概要
本件は、宗教法人である原告が出版する新聞に掲載された写真を、原告の会員である被告がツイッターにおいて複製し掲載したことが、原告が有する写真の著作権(送信可能化権[3])を侵害されたとして、原告が被告に対して損害賠償を請求した事案です。
具体的な被告の行為は、新聞の紙面における写真をスマートフォンで撮影し、その撮影画像を自らの投稿文と共にツイッターに投稿したというものです。本件判決によると、本件の原告は被告による25個の投稿が問題として主張していますが、公開された判決文には、以下の本件投稿1及び2(以下両者を合わせて「本件投稿」といいます。)のみが掲載されています。
本件投稿1
最凶タッグ
【新聞紙面を撮影した画像】
本件投稿2
今日の「寸鉄」
師弟の魂刻む「3・16」。誓願に生きる人は強し!青年よ立ち上がる時は今
師弟の魂刻む「3・16」?誓願より「世界聖教会館」定礎式の扱いが大きい不思議な新聞【新聞紙面を撮影した画像】
(以上、投稿文章につき本件判決より引用)
上記のように、本件投稿にはいずれも新聞紙面をスマートフォンで撮影した画像が添付されていました。それらの画像は、新聞紙面上の写真のみを撮影したものもあれば、新聞紙面上の写真及びその周囲の文章を含むものもありました。
なお、本件投稿1における新聞紙面の撮影画像の内容は、横に並んだ5名の人物が写る写真のみであり、本件投稿2における新聞紙面の撮影画像の内容は、建物を撮影した写真及びその周囲の新聞紙面を含むものです。
本件訴訟にはいくつかの争点がありますが、本稿では、判決文中においても中核的争点と言及された引用の成否を取り上げます。
判旨
まず本件判決は、以下のとおり、著作権法32条1項の判断手法について、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内であるかどうかは、他人の著作物を利用する目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の程度などを総合考慮して判断する旨を述べました。
著作権法32条1項は、公表された著作物は、公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で、引用して利用することができる旨規定するところ、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内であるかどうかは、社会通念に照らし、他人の著作物を利用する目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の程度などを総合考慮して判断されるべきである。
次に本件判決は、被告の行為について、被告が新聞のごく一部の記事をスマートフォンで撮影し、その写真とともにその記事に関する原告に対する批評をツイッターに投稿したものであると認定しました。
そのうえで本件判決は、以下のとおり、仮に本件各写真に創作的表現部分があったとしても、ツイッターに投稿された上記写真に映し出された本件各写真はそのごく僅かな部分を複製するものにすぎないと判断し、その理由として
- 原告の新聞記事は、批評の目的で、スマートフォンの写真1枚に写り込む限度で利用されたものであること
- 本件各写真の構図は総じてありふれたものであること
- ツイッターに投稿された画像に映し出された本件各写真は、全体として不鮮明であり、その画質は粗く細部は捨象されていること
を挙げました。
スマートフォンで撮影された上記記事には、いずれも上記批評と関連するものが含まれており、上記記事は、上記批評をする目的でスマートフォンの写真1枚に写り込む限度で利用されたものである。のみならず、前記認定事実によれば、スマートフォンで撮影された上記記事には、聖教新聞に掲載された本件各写真が含まれているものの、本件各写真の構図は総じてありふれたものであり、ツイッターに投稿された上記写真に映し出された本件各写真は、被告が聖教新聞の紙面に掲載されていたものをスマートフォンで撮影し更にツイッターに投稿したものであるから、全体として不鮮明であり、その画質は粗く細部は捨象されていることが認められる。そうすると、仮に本件各写真に創作的表現部分があったとしても、ツイッターに投稿された上記写真に映し出された本件各写真は、そのごく僅かな部分を複製するものにすぎない。
本件判決はまた、ツイッターに投稿された画像に映し出された本件各写真が独立して二次的に利用されるおそれは極めて低いとし、二次的に利用されたことによって原告が経済的利益を得る機会を現に失ったとは認められないと判断しました。
さらに、ツイッターに投稿された上記写真に映し出された本件各写真の上記態様に鑑みると、その不鮮明な本件各写真が独立して二次的に利用されるおそれは、極めて低いというべきであり、本件全証拠によっても、二次的に利用されたことによって原告が経済的利益を得る機会を現に失ったことを認めるに足りない。
本件判決はさらに、一般の読み手の普通の注意と読み方を基準とすれば、被告の一連の投稿内容に照らし本件各写真の出所を理解することはできる旨も指摘したうえで、以下のように述べ、各事情を総合考慮すれば、被告の行為は公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内であって、著作権法32条1項の引用に該当すると判断しました。
これらの事情の下においては、上記認定に係る本件各写真の性質、その利用目的、ツイッターへの掲載態様、著作権者である原告に及ぼす影響の程度などを、 社会通念に照らして総合考慮すれば、被告が聖教新聞掲載に係る本件各写真をスマートフォンで写してこれをツイッターに掲載して利用する行為は、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内であると認めるのが相当である。
したがって、被告による本件各写真の利用は、著作権法32条1項にいう引用に該当するものであるから、違法なものとはいえない。
コメント
本件判決は、引用の判断につき総合考慮説の立場に立ち、結論として適法な引用を認めたものです。
引用された作品は新聞紙面に掲載された写真であるところ、総合考慮説の枠組みの中で本件判決が適法な引用と認めた主要な理由は、
- 本件各写真に創作的表現部分があったとしてもそのごく僅かな部分が複製されたにすぎないこと
- 本件各写真が独立して二次的に利用されるおそれは極めて低く、二次的に利用されたことによって原告が経済的利益を得る機会を現に失ったとは認められないこと
であると思われます。
特に本件判決では、引用された写真が不鮮明で画質が粗いことなどにより、独立して鑑賞の対象となるものではなく、二次的に利用され原告の経済的利益が損なわれるおそれは極めて低いことに理由として重きが置かれているように思われます。
判決文では審理経過として、裁判所は最後の期日において、原告に対しては被告による利用行為が原告に及ぼす影響に限り主張立証を補充するよう求めた旨の記載がありますが、このような審理経過にも、原告の経済的利益等への影響を重視していた可能性が窺われます。
この点について、同じ中島基至裁判長による東京地判令和5年5月18日・令和3年(ワ)第20472号では、原告が著作権を有する写真が被告のウェブページに掲載されたという事案において、本件判決と同様の総合考慮説の判断基準を示したうえで、引用は成立しないとの判断がされています。その理由としては、商業的価値が高い写真がそれ自体独立して鑑賞の対象となる態様で大きく掲載されていること、無断複製防止措置がされずインターネット上に相当広く複製等されていることから、当該写真の著作権者である原告に及ぼす影響も重大であることが述べられています。
この判決と本件判決との比較も踏まえると、両判決からは、特に写真の著作物について、独立して鑑賞の対象となる態様か、二次的に利用されるおそれがあるかといった点を判断の分かれ目とする考え方が窺われます。
また、本件投稿1の投稿文章が「最凶タッグ」のみであったことからすると、本件判決は、引用する側が著作物であることを適法な引用の要件と考えていないとも理解されます。著作権法32条の条文にない要件を考えないという方向性をとるならば、引用する側の著作物性は要求しない立場に親和性があるでしょう。
これらの点につき、今後の裁判所の判断が引き続き注目されます。
脚注
————————————–
[1] 最判昭和55年3月28日・民集34巻3号244頁。
[2] 高林龍著『標準 著作権法 第5版』(有斐閣、2022年)183頁、島並良ほか著『著作権法入門 第4版』(有斐閣、2024年)192頁
[3] 送信可能化とは、著作権法が定める一定の行為をすることで自動公衆送信され得る状態に置く行為をいい(著作権法2条1項9の5号)、例えばインターネット上にアップロードする行為も送信可能化にあたります。自動公衆送信とは、公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うものをいいます(著作権法2条1項9の4号)。公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として無線または有線で送信をする行為をいいます(著作権法2条1項7の2号)。
本記事に関するお問い合わせはこちらから。
(文責・神田雄)