 知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和5年3月9日、商標登録出願の拒絶査定についての不服審判を不成立とした審決の取消請求において、原告商標(朔北カレー)が引用商標に類似するものではなく、商標法4条1項11号には該当しないと判断し、審決を取り消しました。
知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和5年3月9日、商標登録出願の拒絶査定についての不服審判を不成立とした審決の取消請求において、原告商標(朔北カレー)が引用商標に類似するものではなく、商標法4条1項11号には該当しないと判断し、審決を取り消しました。
ポイント
骨子
- (商標の類否の判断基準) 商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。
- (結合商標における分離観察の可否の判断基準) 複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
判決概要
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第2部 |
|---|---|
| 判決言渡日 | 令和5年3月9日 |
| 事件番号 | 令和4年(行ケ)第10122号 審決取消請求事件 |
| 審決番号 | 不服2021-16353号 |
| 本願商標 | 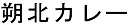 |
| 引用商標 | サクホク(標準文字) 登録第5787174号 |
| 裁判官 | 裁判長裁判官 本 多 知 成 裁判官 浅 井 憲 裁判官 勝 又 来未子 |
解説
商標の登録要件
商標権を取得するためには、特許庁に対して商標登録出願を行い、商標登録を受けることが必要です。
商標の登録が認められるための要件は、以下の通りです。
①自己の業務にかかる商品または役務について使用をする商標であること(商標法3条1項柱書)
②自他商品・役務識別能力があること()条2項)
③不登録事由(3条1項各号、4条1項各号)に該当しないこと
出願商標が不登録事由に該当する場合には、商標登録を受けることができません。
先願に係る他人の登録商標に関する不登録事由(商標法4条1項11号)
日本の商標法においては、商標を先に使用(先使用)していたか否かにかかわらず、特許庁に対して先に商標登録の出願(先願)をした者に商標登録が認められます(先願主義)。
先願登録商標と同一・類似の商標であって、その指定商品・役務または類似の商品・役務について使用するものについては、商標法4条1項11号の不登録事由に該当するものとして、商標登録を受けることができません。
本号は、商標の本質的機能の一つと言われる出所表示機能が阻害されることがないよう、商品・役務の出所混同を防止することを趣旨とするものです。
なお、同趣旨の不登録事由としては、本号の他、商標法4条1項10号から15号の定めがあります(*13号は法改正により削除されました)。
- 4条1項10号:他人の周知商標と同一・類似の商標であって、その周知商標と同一・類似の商品・役務について使用するもの
- 4条1項11号:先願登録商標と同一・類似の商標であって、その指定商品・役務または類似の商品・役務について使用するもの
- 4条1項12号:他人の登録防護標章と同一の商標であって、その指定商品・役務について使用するもの
- 4条1項14号:種苗法上の登録品種の名称と同一・類似の商標であって、その品種の種苗または類似の商品・役務について使用するもの
商標の類否判断
商標の類否判断の基準
商標の類否の判断基準について、特許庁の商標審査基準は、
「出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否⑴かにより判断する」
と定めています(商標審査基準第3十1⑴)。
また、過去の最高裁判例(氷山印事件)は、商標の類否判断について、以下のような判断基準を示しました。
- 商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察する。
- 取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断する。
最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決(氷山印事件)
商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。
類否判断における注意力の基準については、特許庁の商標審査基準は、
「指定商品又は指定役務の需要者が通常有する注意力を基準として判断する」
と定めています(商標審査基準第3十1⑶)。
また、商品・役務の主たる需要者層(例えば、専門的知識を有するか否か、年齢・性別等の違い)や取引の実情(例えば、日用品と贅沢品、大衆薬と医療用医薬品等の商品の違い)を考慮するものとされています(同)。
結合商標の類否判断
結合商標の分離観察の可否
複数の文字や図形、記号等を結合して構成される商標を「結合商標」といいます。
結合商標の類比の判断においては、原則として、商標全体同士を比較して観察することになりますが、構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを比較して類否の判断をすること(分離観察)が許される場合があります。
特許庁の商標審査基準では、結合商標においては、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得るものとされています(商標審査基準第3十4⑴)。
また、過去の最高裁判例(リラ宝塚事件)(つつみのおひなっこや事件)においては、結合商標の類否判断における分離観察の可否や要件について、以下のような判断基準が示されています。
すなわち、結合商標においては、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないときには,その構成部分の一部を抽出し,当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されます。
最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決(リラ宝塚事件)
商標はその構成部分全体によつて他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されない(中略)。しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一六八九頁参照)。
しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。
最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決(つつみのおひなっこや事件)
(商標)法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)。
近時の知的財産高等裁判所における裁判例においても、同様の判断が示されました。
知財高裁平成31年3月12日判決(キリンコーン事件)
複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないときには,その構成部分の一部を抽出し,当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される場合があり,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
事案の概要
経緯
原告は、令和2年2月26日、以下の商標(以下「原告商標」といいます)について登録出願をしましたが、令和3年9月1日付で、特許庁より拒絶査定を受けました。
<原告商標>
商標の構成 
指定商品
第29類: レトルトパウチされた調理済みカレー、カレーのもと、即席カレー、カレーを使用してなる肉製品、カレーを使用してなる加工水産物、カレーを使用してなる加工野菜及び加工果実、カレーを使用してなるなめ物
そこで、原告は、令和3年11月30日、同拒絶査定について不服審判を請求しましたが(不服2021-16353号)、これに対し、特許庁は、令和4年10月21日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」といいます)をし、同年11月2日、本件審決謄本が原告に送達されました。
本件審決の理由
本件審決の理由は、原告商標と以下の商標(以下「引用商標」といいます)とが、互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、原告商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであることから、原告商標は商標法4条1項11号に該当する、というものでした。
<引用商標>
商標の構成 サクホク(標準文字)
指定商品
第29類: 乳製品、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、加工卵、カレー・シチュー又はスープのもと、レトルトパウチされたカレー・シチュー・みそ汁・スープ、豆
第30類: 菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと
判旨
それでは、本判決の判旨を見ていきましょう。
商標の類否判断について
先ず、裁判所は、過去の最高裁判所判決に倣い、以下の通り、商標の類否についての判断基準を示しました。
商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。そして、商標の外観、観念又は称呼のうちの一つにおいて同一又は類似する場合であっても、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、商品の出所に誤認混同をきたすおそれのないものについては、これを類似商標と解することはできない(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
裁判所の示した判断基準は、以下の通りです。
- 商標の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべき
- 商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断する
結合商標における分離観察の可否ついて
次いで、裁判所は、結合商標における分離観察の可否についての判断基準を示しました。
複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
裁判所が示した判断基準は、以下の通りです。
- 商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される
原告商標について
- 原告商標「朔北カレー」は、漢字部分「朔北」と片仮名部分「カレー」からなるもの。
- 「朔北」は、おおむね「北の方角」または「北方の地」を表す単語として理解されるもの。
- 「カレー」は、指定商品との関係では、需要者、取引者は、商品の性質又は原材料を表すものと理解すると認められ、当該部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるということはできない。
裁判所は、このように原告商標の構成等を認定をしたうえで、以下の通り、分離観察が許容されるとの判断を示しました。
本願商標は「朔北」と「カレー」からなる結合商標であるところ、前記のとおり、「カレー」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるということはできない一方で、「朔北」については、需要者、取引者をして、「北の方角」又は「北方の地」を表す単語として理解されるにすぎず、具体的な地域を表すものと理解されるものではないから、指定商品との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じ得るといえる。そして、需要者、取引者をして、「朔北カレー」を一連一体のものとしてのみ使用しているというような取引の実情は認められない。
そうすると、本願商標について、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないから、「朔北」の部分のみを抽出して他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
原告商標と引用商標の類否
裁判所は、以下のとおり、原告商標における「朔北」部分(要部)と引用商標について、外観・称呼・観念を比較し、類否を検討しました。
<外観>
本願要部は「朔北」という2文字の漢字からなるのに対し、引用商標は「サクホク」の4文字の片仮名からなり、外観が明らかに異なる。
<称呼>
本願要部の称呼は「さくほく」であり、引用商標の称呼も「さくほく」であるから、同一である。
<観念>
本願要部からは「北の方角」「北方の地」の観念を生じるものであるのに対し、「サクホク」は、辞書等に掲載されていない造語であって、特定の観念を生じないものであるから、観念が明らかに異なる。
そのうえで、需要者、取引者が商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるとはいえないとして、原告商標が引用商標に類似するとはいえない、との判断を示しました。
本願要部と引用商標は、称呼が共通するものの、外観及び観念は明確に異なっているところ、需要者、取引者が「朔北」から引用商標である「サクホク」や引用商標の権利者を想起するというような取引の実情はなく、また、本願商標及び引用商標の指定商品において、需要者、取引者が、専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないから、本願商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない。
そうすると、本願商標が引用商標に類似するとはいえない。
なお、被告(特許庁長官)からなされた、「朔北」の文字は直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるとの主張(審決では当該主張が採用され、「朔北」の文字からは特定の観念は生じないものと判断されました)は、多数の辞書類に掲載された単語であること、ゲーム内のイベントクエストや小説の題名等にも用いられることがあることなどを理由に、排斥されました。
本判決が審決と異なる結論となったのは、主に原告商標に関する観念についての判断の差異によるものと考えられます
以下のように、審決では、「朔北」の文字からは特定の観念を生じないと判断されましたが、本判決では、「北の方角」「北方の地」という観念が生じるものと判断されました。
| 審決 | 本判決 | |
|---|---|---|
| 外観 | 構成文字の種類及び数において差異を有するものであるものの、両者はともに一般的な書体で表されたもの | 2文字の漢字と4文字の片仮名からなるものであり、明らかに異なる |
| 称呼 | ともに「サクホク」の称呼を生じる | 同一 |
| 観念 | ともに特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない | 「朔北」は「北の方角」「北方の地」の観念を生じるのに対し、「サクホク」は造語であって、特定の観念を生じない |
| 類否判断 | 類似する | 類似するとはいえない |
結論
以上の判断を踏まえて、裁判所は、原告商標が引用商標と類似すると認めることはできず、商標法4条1項11号に該当しないことから、本件審決には取り消し事由が存するものと判断しました。
コメント
本判決は、商標の類否判断や結合商標における分離観察の可否判断についての規範を示したうえで、外観・称呼・観念を丁寧に比較するなど、商標法4条1項11号該当性の判断プロセスがわかりやすく整理されたものであり、実務上参考になるものとして紹介します。








